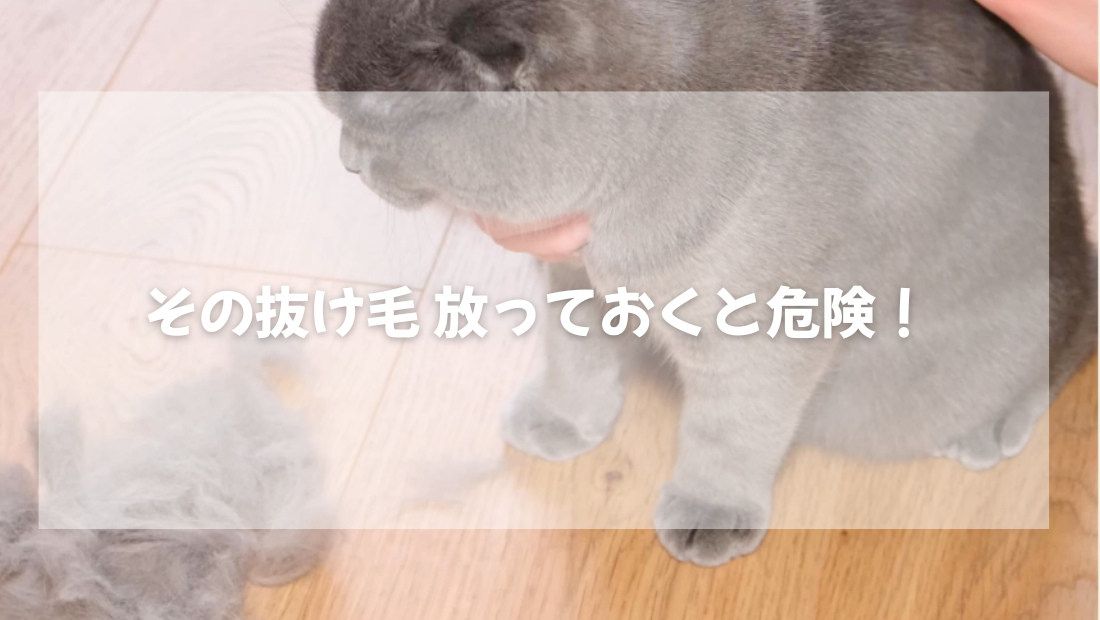
猫の毛球症は、抜け毛を飲み込むことで胃腸に毛玉ができ、食欲低下や吐き気を引き起こす病気です。軽度ならヘアボールとして吐き出せますが、詰まると腸閉塞や脱水につながり命に関わる危険もあります。外で暮らす猫は草木に体をこすって毛を落としますが、室内飼いでは特に注意が必要です。「短毛だから安心」とは言えず、日々のブラッシングや毛玉ケアフード、水分補給が最大の予防策になります。小さな習慣が愛猫の健康を守ります。
その抜け毛放っておくと危険かも…

季節が冬から春、春から夏へと移るたびに、
猫ちゃんの被毛は大きく生え変わります。部
屋の床やカーペット、ソファにふわふわと抜
け毛が増え、「換毛期だな」と感じる瞬間も
多いでしょう。見た目は可愛い抜け毛ですが
、放っておくと健康トラブルの引き金になる
ことがあります。代表的なのが「毛球症(も
うきゅうしょう)」です。
毛球症は、猫が日常のグルーミングで飲み込
んだ毛が、胃や腸でからまり合い、毛玉とし
て固まってしまう状態を指します。自然に吐
き出せたり、便と一緒に排出できればよいの
ですが、出せずに滞留すると、食欲不振、吐
き気、便秘、さらには腸閉塞などの深刻な状
態に進むことがあります。特に換毛期は飲み
込む毛量が増え、リスクが高まります。
「なんとなく元気がない」「吐こうとしても
出ない」「水を飲んでも吐く」――そんな変
化があるとき、実は毛球症が隠れている可能
性があります。短毛種だから安心、というわ
けではありません。今回は、毛球症の基礎知
識、気づくための症状、今日からできる予防
法、短毛種でも油断できない理由を、獣医師
の視点でわかりやすく解説します。大切な家
族を守るために、今からできる一歩を一緒に
確認していきましょう。
毛球症(もうきゅうしょう)ってなに?

猫の舌はザラザラしており、ブラシのように
毛を絡め取ります。毎日の毛づくろいで抜け
毛を自然に飲み込むのは正常な行動です。通
常は胃腸の動きとともに便へと運ばれ、体外
へ排出されます。しかし、抜け毛の量が多い
時期、体質や飲水量の少なさ、腸の運動低下
などが重なると、胃の中や腸管で毛が集合し
、フェルト状の毛玉になります。
毛玉が胃に留まれば、食後の不快感、食欲低
下、嘔吐が目立ちます。腸に進んで詰まると
、ガスや内容物が流れず、腹痛や持続する吐
き気、脱水を招きます。重症では外科手術が
必要になることもあり、「そのうち出るだろ
う」と様子を見るのは危険です。早期発見と
日常の予防が、もっとも効果的な対策になり
ます。
また、毛球は胃に留まるだけでなく、猫が自
力で吐き出す「ヘアボール」として外に出る
場合もあります。これは一見すると健康的に
見えますが、頻繁に繰り返す場合は毛の摂取
量が多すぎるサインかもしれません。吐き癖
が続くようなら、消化器官に負担がかかって
いる可能性があるため注意が必要です。
自然界で暮らす猫であれば、草木や土に体を
こすりつけ、余分な毛を落とすことで毛球症
のリスクを減らしていました。しかし、完全
室内飼いの猫はそうした環境に触れる機会が
なく、グルーミングで取り込んだ毛を自力で
処理しきれないことが多くなります。そのた
め、室内飼いの子ほど毛球症の予防が重要な
のです。
「特別な被毛のケアは要らない」と思われが
ちですが、実際にはブラッシングが最も効果
的な予防法です。毎日数分でもブラッシング
をすることで、飲み込む毛の量を大幅に減ら
すことができます。特に換毛期は、普段より
回数を増やすと良いでしょう。ブラシの種類
も猫の好みに合わせて選び、嫌がらない方法
で続けていくことが、毛球症から愛猫を守る
大切な習慣になります。
こんな症状に注意①

なんとなく元気がない、いつものごはんを残
す、食べ始めてもすぐにやめてしまう。こう
した変化は、胃の中に毛玉が滞留しているサ
インかもしれません。食べ物が毛玉に触れる
たびに気持ち悪さが出て、食欲が落ちるので
す。
普段はよく食べる子が続けて残す、好きなお
やつにも反応が鈍い、寝ている時間が明らか
に増えた――そんなときは要注意。換毛期は
特に、見逃さずに状態を記録し、早めに対処
しましょう。
こんな症状に注意②

「カッ、カッ」とえづくのに、何も出ない状
態が続く。これは毛玉が胃の奥に留まってい
たり、腸管へ移動して引っかかっている可能
性があります。透明な胃液だけを吐く、空え
づきが長引く、えづいた後も落ち着かない――
これらが揃う場合は、自己判断で様子見にせ
ず、早めに動物病院を受診してください。画
像検査や触診で、詰まりの程度や脱水の有無
を評価してもらうことが大切です。
こんな症状に注意③

水を飲んでも吐く、飲んで数分で吐き戻す。
これは胃の出口や腸の通過が妨げられている
危険サインです。短時間で繰り返す嘔吐は、
急速な脱水と電解質の乱れを招き、体力を奪
います。ぐったりしている、口の中が乾く、
皮膚をつまんでも戻りが遅い――そんなとき
は緊急対応が必要です。時間とともに悪化す
るため、「朝まで様子見」は避け、すぐに受
診しましょう。
今日からできる 毛球症予防法

毛球症は日常ケアで大きく減らせます。第一
はこまめなブラッシング。短毛種でも換毛期
は抜け毛が増えます。毎日数分でも、体表に
残る抜け毛を先回りで取り除きましょう。
二つ目は食事。毛玉ケア用フードやサプリに
は、食物繊維や油脂が配合され、便と一緒に
毛を絡めて排出しやすくします。普段のごは
んを急に切り替えるとお腹を壊すことがある
ため、少しずつ混ぜて慣らすのがポイントで
す。
三つ目は水分。器を複数置く、循環式給水器
を使う、ウェットフードを活用するなど、水
をとりやすい工夫をしましょう。飲水量が増
えると腸の動きが助けられ、毛の排出がスム
ーズになります。
四つ目は運動。遊びで腸の蠕動が促進され、
毛の停滞を防ぎます。特に高齢猫では腸の動
きが弱まりやすいため、無理のない範囲で日
常的に体を動かす工夫が大切です。
短毛種でも油断大敵!

「うちは短毛だから大丈夫」と思われがちで
すが、短毛でも毛球症は起こります。毛の一
本一本が短いため、グルーミングで飲み込む
総量は決して少なくありません。特に多頭飼
育では、他の子の毛づくろいをする「相互グ
ルーミング」で、想定以上の毛を取り込んで
しまうことがあります。
また、空調の効いた室内では季節感が薄れ、
一年を通して換毛が起こる子もいます。「今
は換毛期じゃないから大丈夫」という油断は
禁物。月齢、体質、生活環境によって抜け毛
の量は変動します。短毛種でも、定期的なブ
ラッシングと飲水・食事の工夫を続けること
が、最良の予防策です。
獣医師が見た毛球症の実例
診察の現場では、毛球症で来院する猫ちゃん
は決して珍しくありません。例えば、元気が
ない程度で連れてこられた子にレントゲンを
撮ると、胃の中にびっしりと毛玉が確認され
たケースもあります。吐こうとしても出せず
、食欲がなくなり、数日で体重が落ちていま
した。点滴と内服薬で改善しましたが、飼い
主さんは「もっと早く気づいていれば」と後
悔されていました。
逆に、日常的にブラッシングと毛玉ケアフー
ドを取り入れていた家庭では、換毛期でも毛
球症にならず、健康に過ごせている子も多く
います。小さな習慣の積み重ねが、病気の予
防に直結することを、臨床の場で実感してい
ます。
まとめ 大切な家族を守るために
毛球症は珍しい病気ではありませんが、重症
化すると命に関わります。元気や食欲の低下
、空えづき、何も吐けない、あるいは水を飲
んでも吐く――これらは見逃してはいけない
サインです。早めに気づき、無理をさせず、
必要に応じて動物病院へ。
そして何より大切なのは、日々の小さなケア
を積み重ねること。ブラッシングで抜け毛を
減らし、食事と水分で腸の動きを助け、遊び
で体を動かす。短毛種でも油断せず、季節を
問わず続ける。この基本が、猫ちゃんの快適
と安全を支えます。
今日からできる一歩が、明日の大きな安心に
つながります。あなたの手で、愛猫の健康を
守っていきましょう。



