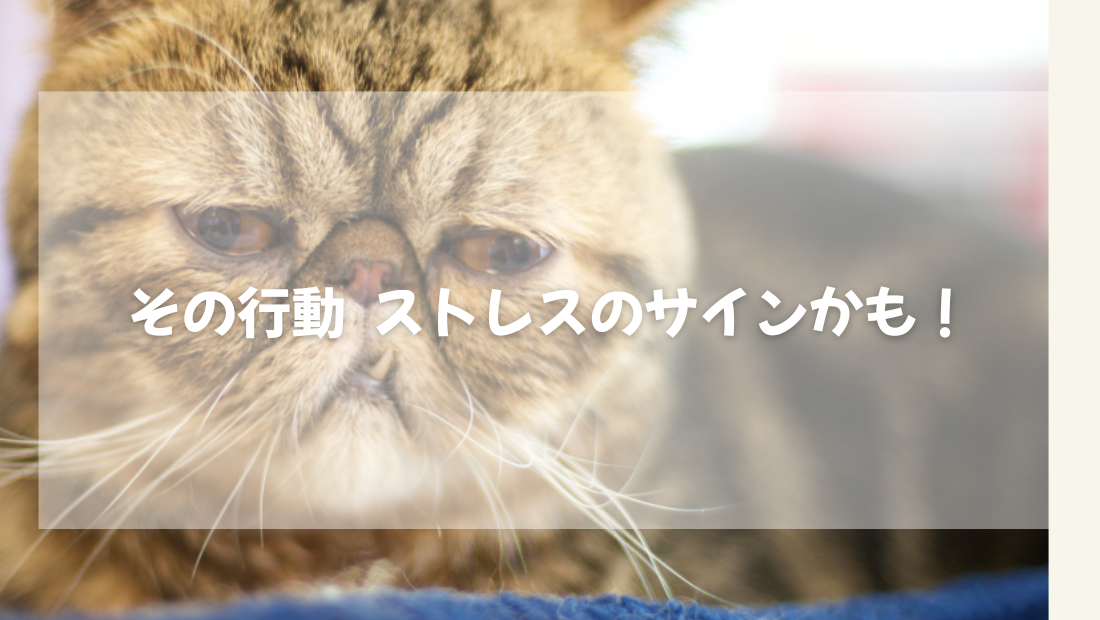
猫は感情を表に出すのが苦手ですが、行動でストレスを伝えてくれています。突然の粗相や攻撃的な態度、嘔吐・下痢など、実は心のSOSかもしれません。日々の小さな変化に気づくことで、猫の健康と安心を守れます。この記事では、ストレスのサインとなる行動を獣医師視点でやさしく解説します。
はじめに
猫は犬のように
感情をストレートに
表現することは少ないと
いわれています。
でも実は、猫も
毎日さまざまな気持ちを
抱えて生きています。
そして、その感情は
「行動」として表れることが多く、
飼い主がそれに気づいて
あげられるかどうかが、
とても大切なのです。
特にストレスを
溜めているとき、
猫は普段と違う行動を
見せることでサインを
出しています。
ところが、そのサインは
一見「気まぐれな行動」や
「性格の変化」として
見逃されてしまうことも。
例えば、急に甘えなくなったり、
鳴く回数が増えたり、
トイレの失敗が増えたりするのも
ストレスの表れかも
しれません。

この記事では、
猫がストレスを感じたときに
見せる5つの行動に注目し、
その理由や対処法を
獣医師の視点から解説します。
日頃のちょっとした変化に
気づき、早めにケアして
あげることで、
愛猫の健康と安心を
しっかり守ることができます。
ストレスを抱えた猫の多くは、
身体の不調だけでなく、
心のバランスも
崩してしまいがちです。
だからこそ、その「行動」を
見逃さず、飼い主ができる
サポートを少しずつでも
始めていくことが、
猫にとっての安心に
繋がるのです。

1. 過剰な毛づくろい
猫は本来、非常に清潔好きな
動物で、グルーミングは
健康管理の一環でもあります。
しかし、ストレスを感じると
この毛づくろいが過剰になり、
同じ部位ばかり舐め続けたり、
毛が抜けて地肌が見えるほどに
なることがあります。
特にお腹や内もも、
前足などの柔らかい部分に、
切毛(毛が短く切れたように
なる状態)や脱毛が見られる
場合は要注意です。
過剰なグルーミングは、
不安や緊張、環境の変化などが
引き金になることが多く、
心の安定を保とうとする
「セルフコンフォート行動」でもあります。
皮膚病やアレルギーとの
鑑別も重要で、痒みがないのに
舐め続けている場合は、
ストレスの影響を疑うべきです。
【対策のヒント】
・安心できるスペースを確保する
・来客や騒音などのストレス源を減らす
・新しい遊びや運動で気を紛らわせる
猫のストレスグルーミングは、
軽度のうちに気づけば
改善が可能です。
習慣化する前に、
環境や接し方の見直しをしてみましょう。

2. 攻撃的になる
普段は穏やかな猫でも、
ストレスが蓄積すると、
突然怒ったり、唸ったり、
攻撃的な態度を取るように
なることがあります。
たとえば、近づいただけで
威嚇したり、急に飛びかかって
きたり、抱っこしようとすると
噛みついてきたりします。
また、夜中に大きな声で鳴いたり、
物を落として暴れるといった
行動も、ストレスによる苛立ちが
原因かもしれません。
このような行動は、
「構ってほしい」「不満がある」
など、猫なりのメッセージで
あることも多く、
単なるわがままとは言い切れません。
急な性格変化や攻撃性の出現は、
甲状腺機能亢進症や痛み、
認知機能の低下が背景にある
場合もあるため、
健康チェックも忘れずに。
【対策のヒント】
・無理な接触を避ける
・静かな環境を整える
・遊びや運動でストレス発散を促す
猫が攻撃的になるときは、
原因があることがほとんどです。
その背景を丁寧に読み取り、
無理せずケアしていくことが大切です。

3. 距離を置こうとする
「いつもは
甘えん坊なのに、
最近そばに来ない…」
そんな行動の変化に
気づいたときは、
猫がストレスを
抱えている
サインかもしれません。
猫は言葉では
伝えられないぶん、
距離の取り方や
行動の変化で
心の状態を
表現しています。
とくに、
以前は飼い主の膝に
よく乗っていた子が、
急に寄ってこなくなったり、
触れようとすると
スッと離れるような
様子が見られたら、
「そっとしておいてほしい」
という意思表示である
可能性もあります。
ストレスや不安が
たまってくると、
猫は過度な接触を
避ける傾向があります。
環境の変化や、
家庭内の音・においなども
影響するため、
まずはその原因を
探ってみましょう。
また、
家族構成の変化や、
家具の移動など
一見些細なことが、
猫にとっては
大きなストレスに
なることも。
【対策のヒント】
・無理に構わず、 猫のペースを尊重する
・いつものお気に入りの場所を確保する
・静かな声で名前を呼び、距離をとったまま見守る時間を作る
そして何より大切なのは、
「距離を取ってきた」
という行動を
マイナスに捉えすぎないことです。
猫なりの方法で、
環境に適応しようと
しているサインなのです。
そんな時こそ、
言葉がけを
意識して増やしたり、
そっと寄り添う姿勢で
信頼関係を
再構築していくことが
大切です。

4. トイレ以外で排泄する
猫は本来、
教えられなくても トイレの砂を使って
排泄できるほど、
とてもきれい好きな 動物です。
そんな猫が突然、
トイレ以外の場所で 排泄をしてしまう場合、
そこには明確な理由が
隠れていることが多いのです。
たとえば、
引っ越しや 家具の移動など、
ちょっとした環境の変化でも
猫は大きなストレスを感じます。
「気に入っていたはずの トイレに入らなくなった」
という場合、
それは単に 気まぐれではなく、
その空間に対して
何らかの不安や違和感を
抱いているサインかもしれません。
また、ストレスだけでなく、
膀胱炎や尿路結石などの 泌尿器系の病気、
糖尿病、腎不全といった
内科的な病気の可能性もあります。
排尿・排便の失敗は、
精神的ストレスだけでなく、
体調不良のサインであることも。
必ず獣医師の診察を 受けるようにしましょう。
【対策のヒント】
・トイレの数や場所、 砂の種類を見直す
・安心できる空間を 増やしてあげる
・排泄の頻度や量、 色、臭いを日頃から観察する
叱ってしまうと、 猫はさらに不安を感じ、
排泄のトラブルが 悪化することもあります。
「なぜそこでしたのか?」を 冷静に考え、
猫の気持ちに寄り添って 対応していきましょう。

5. 嘔吐や下痢
猫の体調不良は、
ストレスからくることも
少なくありません。
特に急激な環境変化や、
飼い主の不在、 生活リズムの乱れなどが
引き金となり、
胃腸に影響が現れることが あるのです。
猫は緊張すると、
胃酸の分泌が増えたり、
腸の動きが過敏になったりするため、
食欲が落ちたり、
嘔吐・下痢といった症状が 出ることがあります。
また、心因性の嘔吐は、
「空腹時に白い泡を吐く」
「食後にすぐ吐いてしまう」
といったパターンも多く、
慢性的になると 体重減少にも繋がるため、
注意が必要です。
胃腸炎、寄生虫、 ウイルス感染など、
他の病気と見分けるためにも、
嘔吐や下痢が続く場合は 必ず動物病院で検査を。
【対策のヒント】
・食事の時間と量を安定させる
・静かな環境でごはんを食べられるようにする
・水分補給をしっかりサポートする
日頃から、
「何回くらい吐いているか」
「下痢の頻度や色は?」
「食欲や飲水量は落ちていないか」
など、細かく観察することが
早期発見につながります。
身体の不調が続くと、
猫の気持ちも不安定になりがちです。
心と体、両方の健康を守るために、
ストレスケアと病気のチェックは
セットで行いましょう。

まとめ
猫のストレス行動は、
私たち飼い主が
気づいてあげることで
早めに対処できます。
過剰な毛づくろい、
攻撃性、排泄トラブル、
嘔吐や下痢──
どれも猫からの
大切なサインです。
「いつもと違うな」
と思った時点で、
すでに猫は何らかの
不安を抱えているかも
しれません。
叱ったり無視したりせず、
その気持ちを受け止めて、
静かに寄り添う姿勢が
求められます。
また、体調不良が
隠れている可能性もあるため、
症状が続く場合は
動物病院での受診も
検討してください。
猫との暮らしは、
小さな変化に
どれだけ気づけるかが
信頼関係を築く鍵です。
猫の気持ちを想像しながら、
無理のない範囲で
環境を整えていくことが、
一緒に暮らす喜びを
より深くしてくれます。
あなたの優しさと観察力が、
猫の心と体の健康を守る
何よりのサポートになります。



