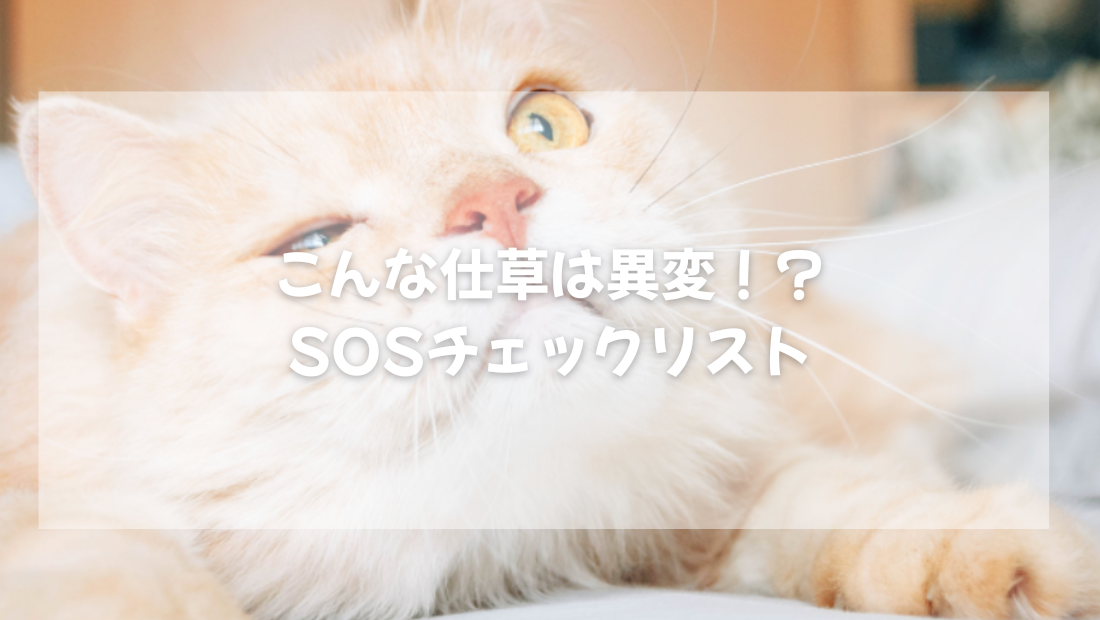
猫は体調不良を隠す習性があり、普段と違う仕草や行動がSOSのサインであることも。食べ方や歩き方、トイレの様子、目の異常、急な甘えや隠れ行動など、日常の中に異変のヒントが隠れています。早期発見のためには、飼い主が小さな変化を見逃さず観察することが大切。本記事ではチェックポイントを具体的に紹介し、猫が不調を隠す理由にも触れながら、病気の早期対応に役立つ情報をわかりやすく解説しています。

猫はもともと、
とても我慢強く
不調を隠す生き物です。
野生時代の名残で、
弱っていることを
まわりに知られないように、
痛みや不安を
態度に出さないように
してしまうのです。
ですが、
完全に隠しきれるわけではなく、
よく観察すると
「いつもと違うな」
と感じるような
小さな変化があります。
たとえば――
食べ方が変わった
歩き方がぎこちない
トイレに異変がある
甘えたり隠れたりと、
行動パターンに違和感がある
こうしたサインは、
猫からの「小さなSOS」。
それに早く気づいてあげられるかが、
命を守るカギになることも
少なくありません。
「何となくいつもと違う」
という違和感があったら、
それはもう大切なサイン。
今回は、猫の体調不良が
隠れているかもしれない
仕草や行動の変化を
チェックリスト形式で
詳しくご紹介します。
猫を飼い始めたばかりの方や、
保護猫との暮らしを始めた方にも
分かりやすく解説しています。
あなたの大切な猫の
「声なき声」に気づく
ヒントになりますように。

食べ方の変化→ 口のトラブルのサインかも
猫が片方の口でしか
噛んでいない、
頭を傾けて食べるように
なったとしたら、
それは口の中に違和感や
痛みを感じている
可能性があります。
よだれが増えていたり、
顔をかくような仕草をする、
口臭がきつくなってきた――
これらも口腔トラブルの
サインのひとつです。
猫は口の中を
なかなか見せてくれません。
だからこそ「食べ方」に
注目することがとても大切です。

【考えられる疾患】
・歯周病
・口内炎
・歯の破折
・口腔内腫瘍
食べ方の変化は、
見逃しがちな病気の初期症状。
特に高齢の猫では
歯肉炎や歯のぐらつきが
よく見られるので、
注意深く観察しましょう。

トイレでの異変→ 泌尿器トラブルの可能性
猫の泌尿器の病気は、
特にオス猫で多く、
急激に悪化することも
あります。
「トイレに行っても
なかなかおしっこが出ない」
「出るたびに鳴く、痛がる」
「おしっこの色がいつもと違う」
これらは
膀胱炎や尿路結石の
サインかもしれません。
放っておくと
尿が完全に詰まってしまい、
命に関わる事態にも。

【考えられる疾患】
・膀胱炎
・尿石症(結石)
・尿道閉塞
・腎不全
トイレの回数や
出ている量、
においや色の変化を
毎日チェックするだけで、
多くの病気を早期に
見つける手がかりになります。
猫砂の変化も含めて
よく観察してみましょう。

歩き方がぎこちない→ 関節・筋肉・ホルモンの異常?
ジャンプをためらう、
爪とぎをしなくなる、
歩き方がよたよたしていたり、
触られるのを嫌がる…。
こんな仕草が見られたときは、
痛みがあるか、
筋肉や関節に問題がある可能性が。
猫は年齢を重ねると
関節が硬くなりやすく、
動きのぎこちなさが
徐々に増えてきます。
【考えられる疾患】
・関節炎(加齢性・遺伝性)
・脱臼や骨折などの外傷
・神経系のトラブル
・糖尿病などのホルモン異常
特にシニア猫では
「動きが少なくなったな」
と思ったら、
それは単なる老化ではなく
病気のサインかもしれません。
日常の動作をよく観察し、
動きの変化には早めに
気づいてあげましょう。

目の様子がいつもと違う→ 眼の病気や高血圧のサイン
「目ヤニが増えた」
「涙が出る」
「瞳孔の大きさが左右で違う」
「まぶしそうにしている」
「目を開けづらそう」
このような症状は、
目に異常があるサインです。
特に高齢の猫では、
高血圧によって
網膜が傷つき、
突然失明することもあります。
また、子猫や若い猫でも
結膜炎や角膜炎などの
感染性疾患にかかりやすく、
目のトラブルは
放置すると悪化しやすいので
早めの対応が重要です。
【考えられる疾患】
・結膜炎
・角膜潰瘍
・高血圧性網膜症
・外傷や異物の混入
目に異常が見られたときは、
自宅で無理に触らず、
動物病院での診察を受けましょう。
「目」はとてもデリケートです。

急に甘える or 隠れる→ 体調不良のサインかも
いつもはツンとしているのに、
急にやたらと甘えてきた――
または、
普段は近くにいるのに
急にどこかに隠れて
出てこない…。
こういった性格の変化も、
猫からのSOSです。
体がだるい、寒気がする、
痛みがある、
などの不調があると、
いつもと違う行動を
とることがあります。
【考えられる疾患】
・発熱
・貧血
・内臓の炎症や腫瘍
・慢性疾患の進行
呼んでも反応が鈍い、
目が合わない、
動きたがらない…。
そんなときは、
「疲れているのかな」で
済ませず、
できるだけ早めに
受診することをおすすめします。
多頭飼いで異変に気づきにくいときは?
複数の猫と暮らしていると、
トイレの回数や
食事の量、
行動の違いに
気づきにくくなります。
「誰が食べたか分からない」
「おしっこは誰の?」
という状況では、
異常が見逃されやすく、
発見が遅れがちです。
【対策のヒント】
・食事やトイレはできるだけ個別に管理
・食器やトイレに名前シールを貼る
・病気になりやすい子は
ペットゲートで別室管理
また、1日数分でもいいので、
一頭ずつ様子を見ながら
スキンシップを取る習慣を
作るのもおすすめです。
ちょっとした変化を
「気のせい」にせず、
日頃の観察力が
命を守る第一歩になります。
猫が不調を隠す理由を知ろう
猫は他の動物に比べて、
体調不良を態度に出しにくい動物です。
それには理由があります。
もともと猫は、
小型の肉食動物として生きてきた
歴史があります。
野生の世界では、
弱っていることを周囲に知られると
すぐに敵に狙われたり、
仲間からはぐれてしまったりと、
生き残るうえで不利になります。
そのため本能的に、
体調が悪くてもできるだけ
「普段どおり」を装うよう
進化してきたのです。
これが、
「猫は病気を隠す動物」
といわれる理由です。
一方で、飼い猫として暮らすようになっても、
この本能は簡単には変わりません。
むしろ室内で安全に暮らしているからこそ、
人間側が異変に気づきにくく、
発見が遅れてしまうこともあるのです。
たとえば、
ぐったりせず普段どおりに歩いていても、
実は関節が痛い、
お腹に不快感がある……
そんな状態のまま
何日も過ごしていることも。
特に多頭飼育の家庭では、
一頭ずつの変化に気づきにくく、
病気の発見が遅れる要因に。
このような背景を理解したうえで、
「何かおかしい」と感じたら
早めに受診する習慣を持つことが
猫の健康寿命をのばすことに
つながっていきます。
猫が言葉で訴えることはできない分、
私たちが行動や仕草から
“心と体のサイン”を読み取ってあげる
姿勢がとても大切です。
「ちょっと変かも?」
その直感こそ、
猫を守る第一歩かもしれません。
猫の不調は、
静かに、さりげなく
表に出てきます。
派手な症状ではなく、
「いつもとちょっと違う」
そんな些細な変化が、
重大な病気のサインだった
ということも少なくありません。
・食べ方が変わった
・トイレの様子が違う
・動きが鈍くなった
・目がうるうるしている
・性格が急に変わった
こうした変化を見逃さずに
「気づいてあげること」
「早めに受診すること」
それが猫の命を守る
何よりの方法です。
不調を隠す猫にとって、
最も頼りになるのは
日々一緒に過ごしている
飼い主のあなたです。
愛猫のSOSに、
あなたが一番に気づいてあげられますように。
そのために今日から、
小さな仕草や変化を
見逃さない「まなざし」を
持ってあげてください。




