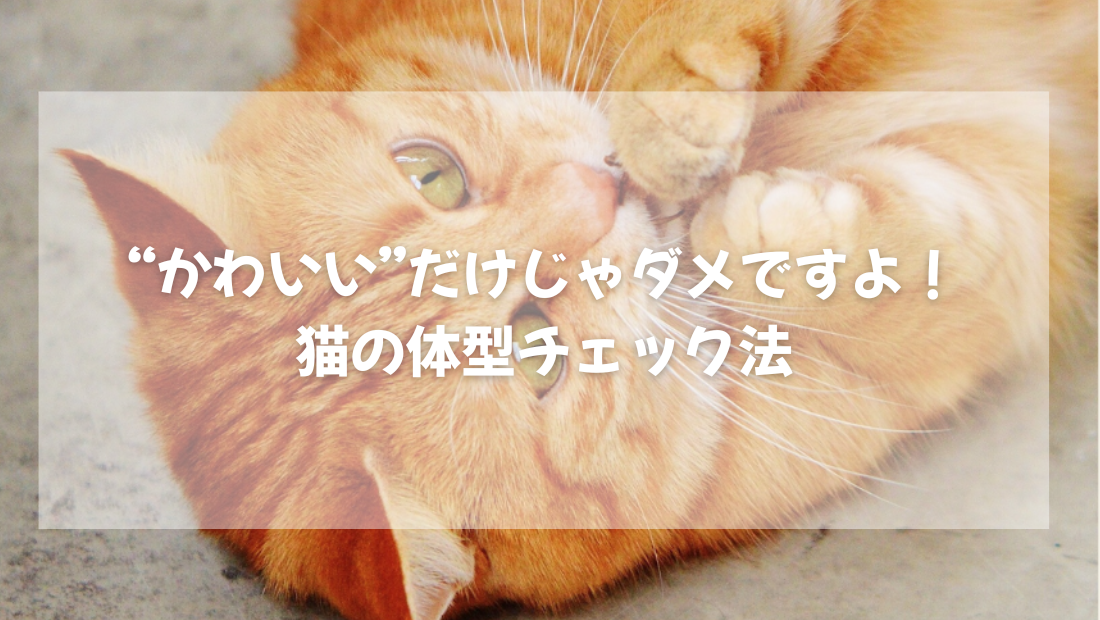
猫の理想体型は体重ではなく「BCS(ボディコンディションスコア)」で判断するのがポイント。触って肋骨が感じられるか、上から見てくびれがあるかをチェックすることで、肥満や痩せすぎの早期発見につながります。筋肉量や年齢によって体重は変動しますが、理想はあくまでバランスのとれた体型。フード管理や日常の遊び、食材選びを工夫し、数字に惑わされない健康維持を意識しましょう。毎日の“触れる習慣”が、愛猫の命を守る最も身近な健康チェックになります。

「ちょっと太ったかも?」
そう感じたとき、
体重だけを見て判断していませんか?
猫の健康管理で最も大切なのは、
見た目の印象ではなく、
体型(ボディコンディション)です。
猫は被毛で体のラインが
わかりづらく、
見た目だけでは
太っているのかどうかを
見極めるのが難しい生き物。
そのため、獣医療の現場では
BCS(ボディコンディションスコア)
という共通の指標を使い、
“触ってわかる健康チェック”
を行います。
理想体型は「BCS3」。
でも、触り方を間違えると
正確な判断ができません。
この記事では、
誰でもできるBCSの見方と、
健康的な体を保つコツを
詳しく解説します。

BCS1 とてもやせている
あばらや背骨がゴツゴツと浮き出ており、
腰骨や骨盤がはっきり見える状態。
筋肉も落ち、
体をさわると角ばった感触があります。
この場合、
食事量や栄養バランスに
問題があることが多く、
消化吸収不良や慢性疾患の
可能性もあります。
「食べているのに太らない」場合は、
早めに病院での受診を検討しましょう。

BCS2 やややせ気味
見た目にはスリムで
健康そうに見えるかもしれませんが、
触ると肋骨がすぐにわかり、
お腹は平らまたはややへこんでいます。
体力が落ちやすく、
免疫も低下しやすいため、
子猫やシニア猫では要注意。
フードのカロリー量を見直したり、
間食や食事回数を増やすことで
回復をサポートします。

BCS3 理想体型
見た目はスリムですが、
上から見ると
腰に軽いくびれがあります。
肋骨は見えませんが、
触るとやさしく分かる。
この状態が
「最も健康的で理想的」です。
筋肉も適度についており、
運動量・食事量・体重のバランスが
整っている証拠。
年齢を重ねても
この状態を維持することが、
長寿猫への第一歩です。

4. BCS4 やや太りぎみ
肋骨が少し触りにくくなり、
お腹がぽっこり。
上から見ると
くびれがほとんどありません。
「かわいいお腹」と思っていても、
実は肥満の入り口。
体重計ではわずかな差でも、
体脂肪は大きく増えていることも。
運動量が減り始めた
4歳以降の猫に
特に多く見られます。

BCS5 太りすぎ
全体的に丸く、
首も太く見える。
あばらはまったく触れず、
腰のくびれも消失。
この段階になると、
糖尿病・関節炎・心臓病などの
リスクが高まります。
ダイエットは焦らず、
「カロリーを減らすより、
フード内容を変える」
が基本。
高タンパク・低脂肪のフードに切り替え、
満腹感を保ちながら
徐々に減量を目指しましょう。

運動しない猫のダイエット
ダイエットというと、
「ごはんを減らす」「ダイエットフードに変える」
と考える方が多いですが、
それだけでは続かないことがほとんどです。
実は、フードに頼らない工夫が
体と心のバランスを保つ秘訣です。
まず大切なのは、「動くきっかけを作る」こと。
高低差を活かした家具の配置や、
おやつを隠して探す“宝探しごっこ”など、
遊びながら自然に体を動かせる環境を整えましょう。
短時間でも、1日数回のじゃらし遊びが
運動不足の解消につながります。
次に、食事の質を見直してみましょう。
カロリーを減らすよりも、
たんぱく質をしっかり確保することが重要です。
筋肉が減ると代謝も下がり、
太りやすい体になります。
ササミや白身魚、茹でたささみスープなど、
高たんぱく・低脂肪のトッピングを
少量加えることで満足感が高まり、
ストレスなく食事量をコントロールできます。
また、野菜を少し加えるのもおすすめ。
猫に与えて安全な食材である
かぼちゃ、ブロッコリー、にんじんなどは、
食物繊維が豊富で便通を整え、
満腹感をサポートします。
ただし、与える際は必ず加熱し、
塩分や味付けをしないことがポイントです。
最後に、生活リズムの見直しも大切です。
1日分のごはんを数回に分けて与えることで、
空腹ストレスを減らし、
血糖値の急上昇を防ぎます。
「遊び→食事→休息」というリズムを作ることで、
猫本来の生活パターンに近づけ、
代謝も安定していきます。
猫のダイエットは、
「減らす」よりも「整える」こと。
無理なく続けられる工夫を
日々の暮らしに取り入れてあげましょう。
体重よりも「体型」を見る
体重計の数値だけで
判断していませんか?
猫の体重は、
筋肉量や骨格の違いで
大きく変動します。
よく運動する猫は
筋肉が発達して
体重が重くても健康そのもの。
一方で、
運動不足の猫は
体重が変わらなくても
脂肪が増えて
体型が崩れていることがあります。
つまり、
「軽い=健康」でも
「重い=肥満」でもありません。
見る・触る・比べる。
この3つが大切です。
肋骨の触り心地、
腰のくびれ、
お腹のたるみ方を
定期的に確認することで、
早期の異変に気づけます。
理想体型を保つコツ
・定期的にBCSをチェック
・月1回は体重を測定
・食事量を「グラム単位」で管理
そして何より大切なのは、
猫の“ライフステージ”に合わせた
ケアを行うこと。
子猫期は筋肉をつくる時期、
成猫期は維持、
シニア期は筋肉の減少を
どう防ぐかがカギです。
「体重が減った=喜ばしい」
とは限りません。
筋肉量が落ちている場合、
免疫力の低下や
関節のトラブルを
招くこともあります。
体型管理の落とし穴
「うちの子はよく食べるけど健康だから大丈夫」
──そう思っていませんか?
実は、体型管理には飼い主が見落としやすい“落とし穴”が
いくつもあります。
たとえば、避妊・去勢後の猫は代謝が落ち、
以前と同じ量を食べても太りやすくなります。
同じフードを続けているだけで、
数ヶ月後にはぽっちゃり体型になることも。
また、多頭飼いでは
「他の子の分まで食べてしまう」ケースがよく見られます。
自由採食(お皿に入れっぱなしのごはん)は便利ですが、
知らぬ間に1匹だけ体重が増えてしまう原因にもなります。
そして、つい甘やかしてしまう「おやつ」も油断禁物。
カロリー量を足してみると、
フードの1食分に匹敵していることも少なくありません。
「ごはん+おやつ+運動量」
この3つのバランスを見直すことが、
体型管理の基本です。
専門家が伝えたい本当の“健康チェック”
猫の健康を守るうえで、
数字だけに惑わされないことが大切です。
体重はあくまで一つの目安。
筋肉量や骨格によって
“理想の重さ”は猫ごとに違います。
私は診察の際、
体重よりもまず「触診」を重視します。
肋骨や腰骨を軽くなで、
皮下脂肪の厚みや筋肉のつき方を
直接感じ取るのです。
そしてもう一つ、
“飼い主さんの気づき”ほど
頼もしいものはありません。
「最近ちょっとお腹が重たそう」
「階段を上がるのが遅くなった」
そんな小さな違和感が、
早期発見につながることがあります。
日常の中で気づける観察眼こそ、
最良の健康管理ツールです。

猫の健康は、
毎日の何気ない観察と
小さな習慣の積み重ねで守られます。
BCSを通じて体型を“触って確認”することは、
単なるチェックではなく、
猫との信頼関係を深める時間でもあります。
「かわいい」だけで終わらせず、
理想体型を維持してあげることが
本当の愛情表現。
ぽっちゃりも、スリムも、
見た目では判断できません。
触れて、比べて、感じ取ることが
健康への第一歩です。
そして、
体型は変わっても性格はそのまま。
少しでも長く、一緒に過ごす時間を
穏やかに楽しむために、
今日から“見る目”を変えていきましょう。



