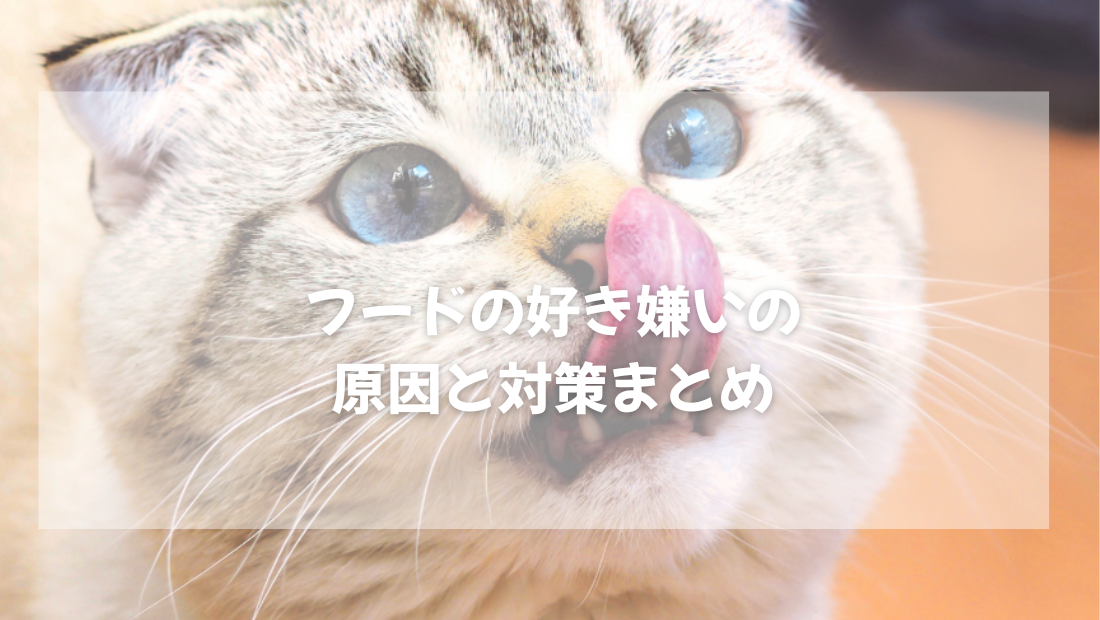
猫がごはんを食べないのは「わがまま」だけが原因ではありません。味や香り、器の形、時間帯、体調などが関係していることも。子猫期の経験やおやつの影響、口の中の痛みも要注意です。本記事では猫の食の好みの背景と対策を、獣医師の視点でわかりやすく解説。愛猫の「食べない」悩みを一緒に解決しましょう。
はじめに
「せっかく買ったのに
まったく口をつけてくれない…」
「ごはんに顔を近づけたと思ったら、
すぐにぷいっとどこかへ」
そんな“ごはん拒否”の行動に
悩まされた経験はありませんか?
とくにショックなのは、
新しいフードを与えたときに
まるで排泄物でもかのように
“砂かけ”の仕草を見せられたとき。
愛猫の健康のためにと
こだわって選んだフードを
否定されたような気持ちになってしまい、
飼い主さんの心も折れてしまいますよね。
 でも、ちょっと待ってください。
でも、ちょっと待ってください。
それ、本当に「わがまま」だけが
原因なのでしょうか?
実は、猫のフードの好き嫌いには
ちょっと意外な背景があるんです。
今回は、猫がフードを食べない理由と、
その対策を獣医師の視点から
わかりやすくまとめてご紹介します。
あなたの猫ちゃんは
どのタイプに当てはまるでしょうか?
少しでも参考になればうれしいです。

原因① 猫は意外とグルメ!
猫は一見なんでも食べそうに見えて、
実はとっても“グルメ”な動物です。
特に、子猫の時期に食べていたフードが
その後の食の好みを大きく左右します。
パウチのウェットタイプに
慣れて育った子は、
ドライフードへの切り替えが
難しくなることがありますし、
逆にドライばかりの子には、
柔らかい食感が受け入れられない
ケースもあります。
また「高ければ食べる」というわけでもなく、
香り、食感、温度といった
“細かなこだわり”が影響します。
中には「このメーカーのチキン味はOK、
でもサーモン味はダメ」というように、
フレーバー単位での好き嫌いもあります。
さらに、子猫期にさまざまな
味や食感の食事を経験しておくことは
偏食を防ぐ意味でもとても大切です。
ドライ、ウェット、半生など
異なる形状のフードだけでなく、
ささみや白身魚、かぼちゃなど
素材そのものの味にも
慣れさせておくと良いでしょう。
“食感の経験”を増やしておくことで、
将来の食生活に柔軟性が生まれます。

原因② おやつのあげすぎ注意
つい「可愛いから」と
おやつをあげすぎていませんか?
猫はもともと狩りをして
空腹時に食べる動物です。
空腹感を覚えないと、
“食べる必要性”を感じず
ごはんに興味を示さなくなります。
また、おやつは
脂肪分・塩分が高く、
嗜好性が強いものが多いため
フードを「物足りなく」
感じさせてしまうことも。
人間で言えば、お菓子ばかり食べて
ごはんを残すような状態ですね。
1日の摂取カロリーに対して、
おやつは10%以下が理想です。
また、フードをずっと置きっぱなしにせず、
決まった時間に与え、
食べ残しは片付けるようにしましょう。
こうすることで猫は
「今食べないとしばらくごはんがない」
という意識を持ちやすくなり、
空腹感を感じる時間も作られます。
これが「食欲スイッチ」を
オンにするきっかけになるのです。

原因③ 食欲不振は病気のサインかも
「うちの子はグルメだから」
と簡単に片付けてしまう前に、
体調面のチェックも大切です。
猫の食欲不振は、
内臓の異常、歯の痛み、
ストレスなど
さまざまな原因と関係しています。
特に気をつけたいのは、
まったく食べない状態が
1日以上続くケース。
猫は絶食が続くと
脂肪肝を引き起こし、
命に関わる状態になることがあります。
少しでも食べる様子があるか、
水分を摂っているか、
排便・排尿の状態に変化がないか
しっかり観察しましょう。
また、意外と見落としがちなのが、
口の中のトラブルです。
歯肉炎、口内炎、折れた歯など、
痛みをともなう状態では、
お腹が空いていても
食べられないことがあります。
お口を開けて見てみるのは難しいかもしれませんが、
よだれが増えている、
食べる時に顔をしかめる、
ごはんを途中でやめてしまうなど、
異変を感じたら要注意です。
健康管理の一環として、
お口の状態を日頃からチェックする
習慣を持つことをおすすめします。

対策① 香りUPで食欲刺激
猫の食欲は「香り」で左右されます。
人間と比べて、
猫はにおいの識別能力に優れており、
フードの香りが立たないと
興味を示さないこともあります。
そこでおすすめの方法が、
・ウェットフードを混ぜて香りをプラス
・ドライフードにお湯をかけてふやかす
・電子レンジで数秒温める
といった工夫です。
とくに冬場は
フードが冷たくなりがちなので、
人肌程度に温めると◎。
香りがふわっと立ち上がり、
猫の嗅覚を刺激してくれますよ。
香りの強い鰹節やささみの煮汁を
少量加えるのも効果的です。

対策② 食べやすい器に変える
「器を変えたら食べるようになった」
という話、実はよくあります。
猫のヒゲはとても敏感で、
食器のフチにヒゲが当たることで
ストレスを感じる子もいます。
そのため、以下のような器を
選んでみると良いでしょう。
・ヒゲが当たりにくい広くて浅い器
・安定感のある陶器の器
・少し高さや傾斜がある器
高さのある食器は
首や背中への負担も軽減されるため、
高齢の猫にもおすすめです。
また、猫は“変化を嫌う”一方で、
“選択肢を与える”ことで
安心して好みを表現できる動物でもあります。
たとえば、器の素材や形を変えて、
いくつか並べて様子を見るのも
ひとつの工夫です。
陶器、ステンレス、プラスチックなど、
素材によって感じ方が異なることもあります。
ある日はAの器で食べ、
別の日はBを選ぶという
気まぐれなパターンがあるかもしれません。
加えて、食事の時間帯にも
注目してみましょう。
人間にも「朝型・夜型」があるように、
猫にも活動のリズムがあります。
一般的には猫は“夜行性”で、
夜〜早朝にかけて活発になることが多いため、
朝はあまり食が進まない子も
少なくありません。
それなのに朝にだけ
食事を置いていると、
「食べない」という印象が
強くなってしまいます。
いつも残してしまう子でも、
時間を夜に変えてみることで、
急に食べ始めるケースも。
一度、愛猫の活動リズムを観察して、
食事の時間帯を見直してみると
意外な発見があるかもしれません。

対策③ 好みを探してみよう
もしも偏食が続くようであれば、
いっそ“好みを探す旅”に
出てみるのもひとつの方法です。
最近では療法食であっても
味や食感にバリエーションがあり、
試供品を取り寄せることで
猫の好みに合ったものを探せます。
また、フードへの“ちょい足し”として
・鰹節
・またたび粉
・チキンのゆで汁
などの香り高いものを
少量だけトッピングするのも◎。
ただし、腎臓病などの持病がある場合は
使用に注意が必要です。
猫の好みと健康の両立を目指しましょう。

まとめ
猫がごはんを食べない背景には、
「好み」「習慣」「体調」など
さまざまな要因が複雑に絡んでいます。
決して「わがまま」だけでは
片付けられないケースが多いのです。
だからこそ、愛猫が
“なぜ今これを食べたくないのか”を
読み解こうとする姿勢が大切です。
猫は言葉で伝えられない分、
行動や仕草で多くのことを
私たちに教えてくれています。
毎日同じものを出していても、
気温や気分、前日の運動量など、
ちょっとした変化で
食べ方が変わることも珍しくありません。
ときには手をかけた工夫が
まったく通用しない日もあるでしょう。
それでも、あきらめずに
観察と工夫を積み重ねていくことが、
信頼関係を深めることにつながります。
猫の立場に立って観察し、
できる工夫を一つずつ試してみる。
それだけで、食べるようになることも
少なくありません。
猫との暮らしは、試行錯誤の連続です。
でも、そのひとつひとつが
信頼関係を深めてくれる
大切な時間でもあります。
愛猫が健やかに、そしておいしく
毎日を過ごせますように🐾



