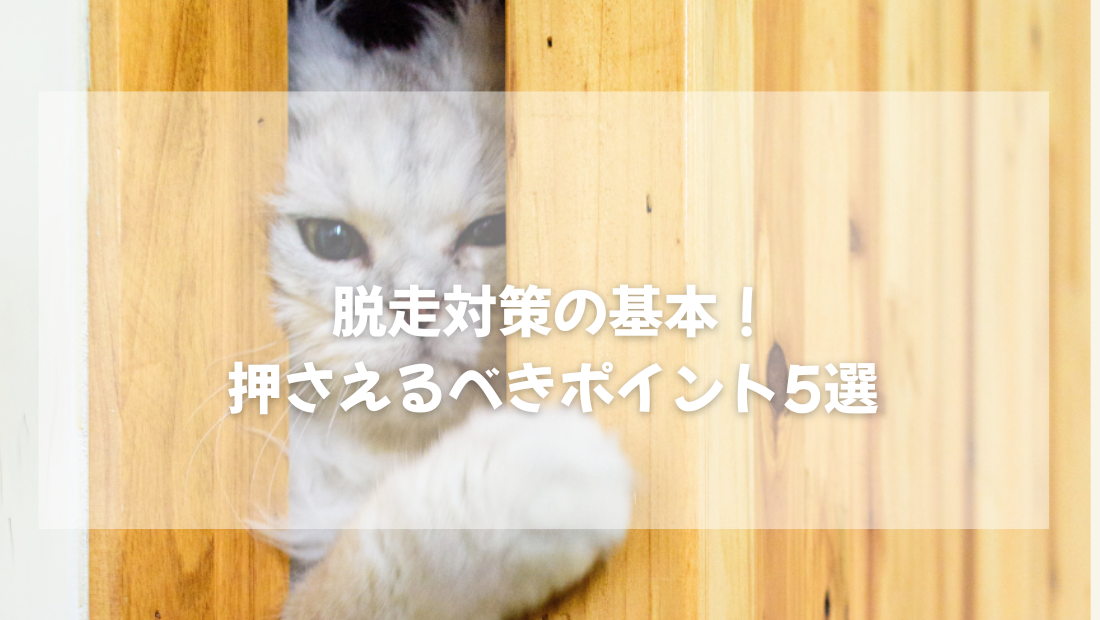
猫の脱走は一瞬の油断で起こり得ます。玄関や窓の対策、スキマの確認、室内遊びの充実、迷子対策、家族での情報共有など、5つの基本ポイントを押さえて備えることが大切です。シチュエーションを想像し、脱走リスクを減らしましょう。
はじめに
「うちの子は
絶対に逃げないから大丈夫」
そう思っていたのに、
ふとした瞬間に脱走してしまい、
パニックになった…という話は
少なくありません。
特に、保護猫を迎えたばかりのご家庭や、
まだ家に慣れていない猫にとっては、
環境の変化や不意の音などが
大きなストレスや驚きになり、
とっさに外へ飛び出してしまうことも
十分あり得るのです。
猫はとても賢く、
そしてとても柔軟な身体を持った動物です。
思いもよらない小さなスキマから
体をねじ込んで抜け出したり、
網戸を押し破ったり、
扉の開く音を覚えてタイミングを見ていたり、
驚くような行動をとることがあります。
また、一度外の世界に出てしまうと、
その記憶が残り、
“また外に出たい”という
欲求が芽生えることもあるため、
脱走は未然に防ぐのが
何よりも大切です。
本コラムでは、
猫の脱走を防ぐために
「絶対に押さえておきたい基本の5ポイント」
について、獣医師の視点から
具体的かつ実践的にお伝えします。
これから猫との生活を始める方にも、
すでに一緒に暮らしている方にも、
今一度、ご自宅の脱走対策を
見直すきっかけとなれば幸いです。

1.玄関&窓の対策を徹底
脱走の原因として
圧倒的に多いのが、
玄関や窓からのすり抜けです。
「宅配便が来てドアを開けた瞬間に…」
「網戸にしていた窓を破って…」
というケースは
決して珍しくありません。
まず、玄関対策として有効なのが
ペットゲートの設置です。
玄関ドアと部屋の間に
物理的な障壁を作ることで、
人の出入り時の飛び出しを
未然に防ぐことができます。
最近では、
突っ張り式で工事不要のものや、
おしゃれな木目調のゲートなどもあり、
インテリアになじみやすくなっています。
また、窓の網戸だけに頼るのはNGです。
網戸は外れやすく、
猫が体当たりしたり
爪をかけて破いたりすることもあります。
・脱走防止用の金網を固定する
・ストッパーで開閉幅を制限する
・脱走防止ネットを取り付ける
といった対策を複数重ねておくことで、
万が一に備えることができます。
夏の暑い時期に換気したい場合も、
これらの工夫をしていれば安心ですね。
そしてもうひとつ大切なのが、
脱走につながるシチュエーションを
あらかじめ想像しておくことです。
たとえば——
・宅配業者が来てドアを開けた瞬間
・子どもが窓を開けて換気したとき
・ゴミ出しで玄関を一時的に開けたとき
このような
“人が動くタイミング”と
猫の好奇心が重なるとき
が、脱走の引き金になります。
家族の行動や生活パターンの中に
どんなリスクがあるか、
一度立ち止まって想像してみましょう。

2.スキマを徹底チェック
猫はとても柔軟で、
細い体を使って驚くほど狭い場所にも
入り込むことができます。
そのため「このくらいのスキマなら平気」
という油断が、
思わぬ脱走につながることもあります。
特に危険なのは
ベランダや窓のすき間です。
サッシや網戸のちょっとした隙間から
顔や前足を差し込み、
器用にこじ開ける猫もいます。
一般的に猫は2cmあれば前足が入るとされ、
4~5cmの隙間があれば
体を押し込んで外に出てしまうことも。
ベランダの下や
エアコンのホース用の穴、
換気扇や物置の裏など、
“猫にとって都合のいい出口”は
私たちが思う以上に多いものです。
また、網戸と窓の間の
“少し開いているだけ”のスペースや、
古くなったサッシのゴムパッキンの隙間も、
猫は爪や鼻でこじ開けて
脱走のきっかけを作ることがあります。
定期的に「猫目線」で
部屋の中や外との接点を
見直すようにしましょう。
特に、季節の変わり目や
引っ越し・模様替えの後などには、
スキマの状況が変わっている可能性があります。
網戸のゆるみや、
家具の隙間、新たな配線ルートなど、
猫が脱走経路として使える場所が
増えていないかチェックする習慣をつけましょう。
“うちの子はもう慣れているから”と
思っていても、
脱走対策は一度で終わるものではなく、
定期的に更新すべきものなのです。

3.好奇心を満たして
外に興味を持たせない工夫
脱走の動機には
「好奇心」が大きく関係しています。
特に若い猫や元気な保護猫は、
外の音、匂い、動きに敏感に反応し、
興味を持って近づこうとします。
ですが、ここで
「ちょっとならいいか」と
庭に出してしまうと、
外は“行ってもいい場所”だと学習し、
次は自分の力で出ようとします。
そのため、日光浴や散歩目的で
外に出すことは控えるのが安全です。
さらに、野良猫との接触があると、
縄張り意識や発情のきっかけになり、
脱走の欲求が一気に高まることも。
外の世界に興味を持たせないためには、
家の中で好奇心を満たす環境づくりが
とても大切です。
・高低差のあるキャットタワーを設置する
・1日2〜3回、時間を決めて遊ぶ
・おもちゃの種類をローテーションする
こうした日常の中で、
「室内でも楽しい」と思わせることが、
脱走欲求を抑える最大の対策になります。

4.もしもの時に備えて
首輪や迷子対策をしておく
いくら対策をしていても、
100%脱走を防げるわけではありません。
だからこそ、脱走後に備えることも
とても大切なポイントです。
まず基本となるのが、
迷子札つきの首輪です。
猫の名前と連絡先が記載されていれば、
保護されたときに
飼い主の元に戻る確率が
格段に上がります。
ただし、外れるタイプの首輪を選び、
首回りに余裕を持たせるなど、
安全面には十分注意を。
さらに、最近では
GPS機能付きの首輪やタグも
普及しています。
スマホと連携すれば、
万が一の脱走時に居場所の手がかりとなり、
発見が早まる可能性があります。
そして、獣医師として特におすすめしたいのが、
マイクロチップの装着です。
体内に埋め込むため外れず、
首輪が取れてしまっても
個体識別が可能です。
動物病院や保健所などで
読み取りができるので、
万が一の迷子時の命綱になります。
5.逃げた時に備えておく
脱走が発生したとき、
すぐに行動できるかどうかは
事前の準備次第です。
まず用意しておきたいのが、
猫のお気に入りアイテム。
・大好きなフードやおやつ
・音のするおもちゃ
・飼い主の匂いがついた毛布
これらを使って、呼びかけながら
家の周囲をゆっくり探すことで、
安心感を与えて出てくることがあります。
家族で探しても手がかりがない時は
迷子猫捜索のプロのペット探偵の助けを借りる方法も
検討してください。
また、普段から
「名前を呼ぶと寄ってくる」ように
しておくと、
いざというときに役立ちます。
・毎日呼びかけておやつをあげる
・特定の音(おやつ袋を振る音など)を
合図にする
こうした呼び戻しの練習は
遊びの一環として取り入れておくと良いでしょう。
日常の中で、
「反応する音や行動」を知っておくことも
いざというときの手がかりになります。
そしてもうひとつ、
家族全員で“脱走リスク”を共有しておくことも
大きな備えになります。
いくら飼い主が気をつけていても、
玄関を開け放ったり
窓のロックを忘れたりするのは、
他の家族かもしれません。
「どの場所に脱走のリスクがあるか」
「どんな場面で起こりやすいか」
を家族みんなで話し合い、
共通認識を持つことが、
もっとも基本で強力な脱走防止策です。

まとめ
猫の脱走は、
決して珍しいことではありません。
ほんの数秒の油断が
命の危険につながることもあるため、
「うちの子は大丈夫」ではなく、
「うちの子を守るにはどうするか」を
常に意識しておくことが大切です。
今回ご紹介した5つのポイントは、
すべて今日から実践できるものばかりです。
・玄関や窓の対策を見直す
・家の中のスキマをチェックする
・室内での遊びを充実させる
・迷子防止策を整える
・もしもの備えを準備する
この機会にぜひ、
あなたのおうちの“脱走危険ゾーン”を
見直してみてくださいね。
愛猫がいつまでも
安心して暮らせるよう、
私たちにできる備えを
一緒に整えていきましょう。




