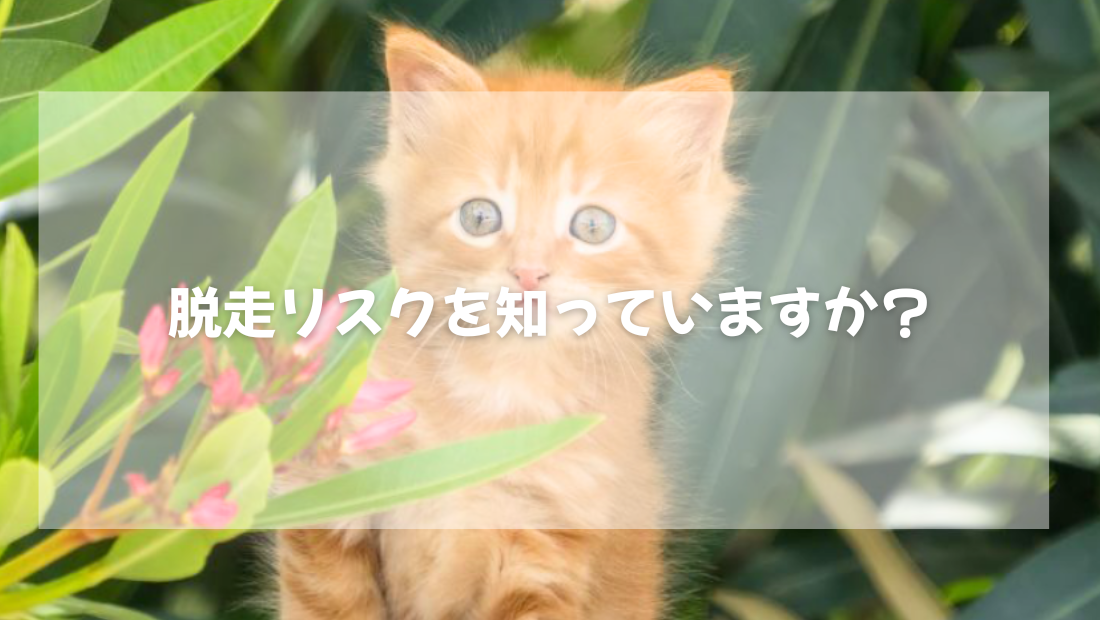
猫の脱走は、年齢や性格に関係なく誰にでも起こりうる身近なリスクです。
発情期や好奇心、ストレスなど、猫自身の“きもち”が行動に大きく影響します。
本記事では、子猫から高齢猫までの脱走傾向とその対策を獣医師の視点からやさしく解説。
「うちの子は大丈夫」と思う前に、できる備えを一緒に考えてみませんか?
はじめに
猫との暮らしは、
毎日が癒しと発見に
満ちた素晴らしいものです。
けれど、その一方で、
私たち飼い主が思いもよらない
瞬間に、愛猫が外に飛び出して
しまう、「脱走」というリスクが
常に身近にあることを
忘れてはいけません。
 「うちの子は大人しいから大丈夫」
「うちの子は大人しいから大丈夫」
「窓やドアは閉めてるから平気」
そう思っていた方が、ある日突然、
愛猫を見失ってしまった——
そんな話は珍しくありません。
猫は年齢や性格、そして体調や
環境の変化によって、
その行動や心理状態が
大きく変化します。
すべての年齢の猫に
脱走のリスクが潜んでいます。
さらに、脱走によるリスクは
迷子や交通事故だけではありません。
感染症のリスク、野良猫とのトラブル、
人間との接触によるケガなど、
外の世界には危険が潜んでいます。
完全室内飼いの猫は
外に適応する力が弱いため、
極度のストレスでパニックを起こしたり、
体調を崩すことも。
「たまたま開けたドアから出てしまった」
「窓のロックが甘かった」
そんな些細なことが、
愛猫との突然の別れに
つながってしまうのです。
だからこそ、飼い主として
「脱走を前提に考える」ことが
とても大切です。
この記事では、猫の年齢ごとに
起こりやすい脱走の傾向と
その対策を獣医師の視点から
解説していきます。
猫は“脱走したくて脱走する”
わけではありません。
そこには不安、ストレス、
好奇心や本能といった
「猫の気持ち」があります。
それを理解し、寄り添うことで
大切な命を守ることができるのです。
1. 生後2〜5ヶ月(好奇心が芽生える時期)
 この時期の子猫は、
この時期の子猫は、
世界すべてが新鮮で、
見るもの聞くもの、
すべてに興味津々です。
生後2〜5ヶ月は、
視覚や嗅覚、運動機能が
ぐんぐん発達していく時期。
この探求心が旺盛な時期に、
室内のあらゆる場所を
自由に歩き回りながら、
“自分のテリトリー”を
確かめていきます。
その過程で、窓際や玄関、
扉の隙間といった、
本来立ち入ってほしくない場所に
興味を持つことも
増えてきます。
特に注意したいのは、
まだ体が小さいために、
大人の猫なら入れないような
わずかなすき間にも
容易に入り込めてしまうことです。
また、柔軟性が高く、
ジャンプ力やすばやさも
急激に伸びてくるため、
飼い主の目が届かないところで
思いがけない行動を
とることもあります。
この段階での脱走リスクは
そこまで高くはありませんが、
“脱走できてしまう環境”があると、
今後の習慣やクセに
なってしまうおそれもあるため、
早いうちから予防を意識した
環境づくりが重要です。
【この時期の脱走対策】
-
小さなすき間や家具の裏に
バリケードを設ける -
窓やベランダには
ロック付きストッパーをつける -
子猫用ケージやサークルなどで
行動範囲を一部制限し、
安心できる場所を用意する
この時期に「安全な探検は楽しい」
という経験を積ませることで、
今後の問題行動を防ぐ
土台にもつながっていきます。
2. 生後6ヶ月〜1歳(性成熟期)

この時期の猫は、
体が大きくなり、
活発に動き回るだけでなく、
性ホルモンの影響によって、
行動が大胆になってくる頃です。
特に未去勢・未避妊の猫は、
本能的な欲求に突き動かされ、
発情期になると
強い衝動により外に出たがる
行動が目立ってきます。
オス猫はメスのにおいに反応し、
扉や窓の前で鳴き続けたり、
脱走を試みることもあります。
メス猫も同様に、
落ち着きがなくなり、
外を見つめながら
鳴くなどの行動を示します。
この時期に脱走してしまうと、
交尾や妊娠のリスクだけでなく、
野良猫とのケンカ、
感染症など多くの問題を
引き起こすおそれがあります。
また、この時期の猫は
運動能力も高まり、
驚くような高さを飛び越えるなど、
予想を超える動きを見せるため、
これまで安全だと思っていた場所でも
油断は禁物です。
【この時期の脱走対策】
-
去勢・避妊手術を
早めに検討・実施する -
外が見えないような
カーテンや目隠しを使う -
鳴き声や落ち着きのなさに
気づいたら、
室内での遊びやスキンシップで
エネルギーを発散させる
この時期を穏やかに乗り越えるためには、
飼い主の理解と対応力が
とても大切です。
3. 1歳~3歳(若年期)

1歳を過ぎると、猫の体は
完全に成猫として成熟し、
筋肉も発達して運動能力が
ピークを迎えます。
この時期は、好奇心も強く、
自分のテリトリーに対する意識も
高まってくるため、
脱走への衝動が
より現実的になってきます。
また、まだ若く体力があるため、
“今すぐに外へ出たい”という
一瞬の衝動に任せて
玄関や窓から飛び出してしまう
ケースも多く見られます。
特に、来客時のドアの開閉、
宅配の受け取りなどのタイミングで、
人のすき間をすり抜けて
外に出てしまうことがあるため、
家族全員が注意する必要があります。
【この時期の脱走対策】
-
来客時・宅配対応時には
玄関前にペットゲートを設置 -
高いジャンプ力にも備えた
高さのある脱走防止柵を導入 -
好奇心を満たせるように、
室内で上下運動や探検遊びが
できる環境を整える
この時期は、活発で自由を
求める傾向が強いため、
「行動のエネルギーを満たす」ことが
脱走防止の大きなカギとなります。
4. 高齢期(7歳以降) 7歳を超えると、猫は徐々に
7歳を超えると、猫は徐々に
高齢期に入り、
活動量や好奇心も少しずつ
落ち着いていきます。
一見すると脱走リスクが
減ったように感じられますが、
油断は禁物です。
高齢猫は環境の変化に
敏感になるため、
引っ越しや家族構成の変化、
新しいペットの導入などが
強いストレスになることがあります。
そのストレスから「逃げたい」
という思いが高まると、
普段は行かない窓辺や玄関へ
近づき、脱走のきっかけを
つくってしまうこともあります。
また、加齢に伴って
視力や聴力が低下することで
周囲の状況を判断しにくくなり、
不安から突発的な行動をとる
ケースも見られます。
【この時期の脱走対策】
-
生活環境をできるだけ変えず、
安心できるルーティンを守る -
不安のサイン(隠れる・鳴く)に
敏感に気づいてケアをする -
ベッドやトイレなど、
生活の基本アイテムは
猫が落ち着ける場所に配置 -
窓や玄関の鍵は二重ロックを心がけ、
外への動線には物理的な対策を設ける
高齢猫にとって「変わらない日常」が
もっとも安心できる環境です。
だからこそ、
ちょっとした変化にも配慮し、
安全と安心を提供してあげる
心づかいが欠かせません。
5. 体調不良期(病気・終末期)

猫は体調が悪くなると、
そのことを隠そうとする
習性があります。
本能的に「弱った姿を見せない」
という生き物としての防衛本能が、
人目のつかない場所を
求める行動に
つながることがあります。
病気や老衰が進むと、
猫は静かな場所を探し、
部屋の隅や家具の裏、
ときには外へ出てしまい、
姿を消してしまうことも
少なくありません。
「いつもいる場所にいない」
「名前を呼んでも反応がない」
そんなとき、
すでに脱走していた
というケースもあります。
また、死期が近づいた猫が
自分の最期を静かに
迎えようとして
外に出てしまうという話も、
決して珍しくありません。
この時期の脱走は、
迷子や事故のリスク以上に、
飼い主にとって
精神的なショックが
とても大きいものです。
【この時期の脱走対策】
-
窓やドアに脱走防止ゲートを設置
-
隠れられる安心スペースを用意し、
無理に動かさずに見守る -
行動範囲を絞って、
一部屋で過ごせる環境を整える -
できるだけ目を離さず、
体調に変化がないか観察する
体調不良期こそ、
物理的な対策とともに、
愛情と気づかいのあるケアが
求められます。
まとめ|脱走は“誰にでも起こる”

猫の脱走は、
特別なことではありません。
性格に関係なく、
どの年齢でも、
ちょっとしたきっかけで
起こってしまう可能性があるのです。
「うちの子は大丈夫」
「普段は落ち着いているから」
という油断が、
取り返しのつかない事態を
引き起こすことがあります。
だからこそ、飼い主として
“先回りして備える”ことが
とても大切です。
猫の年齢や性格を理解し、
その段階に応じた
脱走防止対策を行うことで、
愛猫の命と暮らしを
守ることができます。
とくにペットゲートは、
猫の行動範囲を
安全にコントロールできる、
シンプルで効果的な
アイテムのひとつです。
家のつくりや猫の性格に合わせて、
適切な場所に設置すれば、
安心感のある暮らしが叶います。
猫にとって家は
「もっとも安心できる場所」
であるはずです。
その安心を守るために、
今日からできる対策を
ひとつずつ始めていきましょう。



