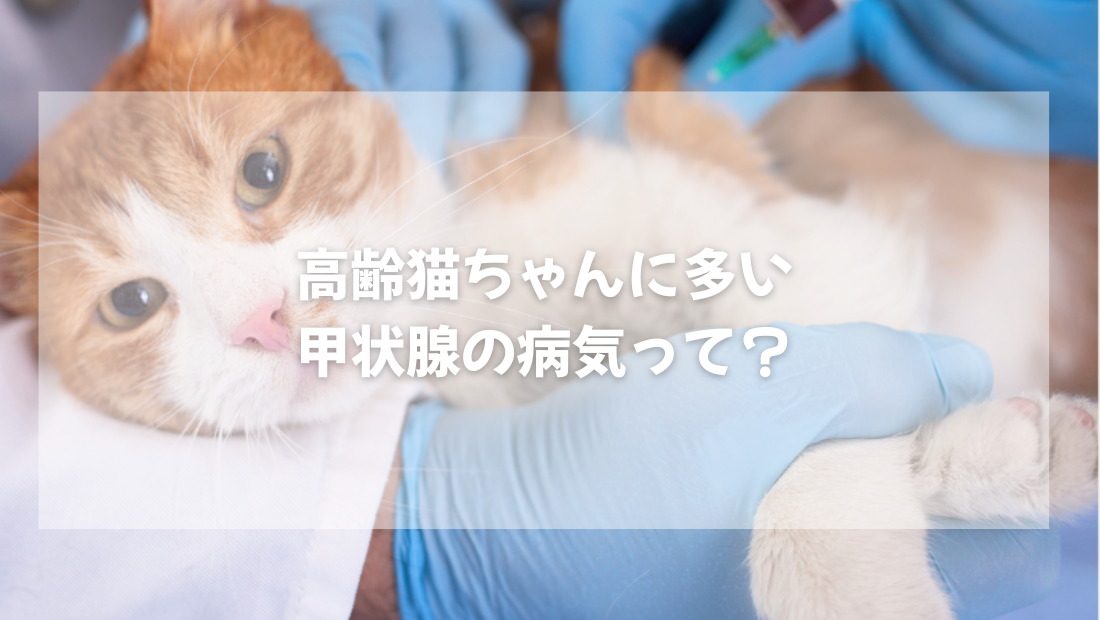
高齢猫に多い「甲状腺機能亢進症」は、元気に見える行動が病気のサインになっていることがあります。よく食べるのに痩せる、夜中に走り回る、鳴き声が増えるなど、一見若返ったように見える変化も要注意。放置すれば心臓や腎臓へ負担がかかり、命に関わることも。腎臓病や糖尿病、高血圧など他のシニア猫に多い病気とも似ているため、見た目に騙されず定期検診で確認することが健康寿命を延ばすカギです。
 「最近、うちの子が元気になった」
「最近、うちの子が元気になった」
「前より食欲もあるし若返った?」
そんなふうに感じたことはありませんか。
もちろん元気なのは嬉しいことですが、
その裏に病気が隠れている場合があると
したら…どうでしょう。
高齢の猫に多く見られる
「甲状腺機能亢進症」は、
一見すると「活発で元気」
に見えるため、発見が遅れやすい病気。
よく食べるのに体重が減る、夜中も走り
回って落ち着かない、
鳴き声が大きくなるなど、
一見“元気に見える変化”が
サインになっていることもあります。
シニア期に入った猫ちゃんに、こうした
様子が見られるなら要注意。実は体内で
代謝が暴走し、心臓や腎臓に負担がかかる
危険な状態かもしれないのです。
今回は、そんな「甲状腺機能亢進症」
について、症状・リスク・早期発見の
ポイントをわかりやすくまとめました。

こんな症状、思い当たりませんか?
・食べているのに痩せていく
・以前よりよく鳴くようになった
・夜も走り回って寝ない
・ごはんの催促が止まらない
一見「元気で若返った?」と思う変化も
実は要注意のサインです。特に食欲が
あるのに痩せていく場合は典型的。
また、落ち着きがなくなり夜中に運動会
をするようになる子も多く、飼い主の
生活にも影響します。

一見“元気そう”に見えるのが落とし穴!
甲状腺機能亢進症の怖いところは、病気が
進んでいても猫が「元気いっぱい」に見え
てしまうことです。
飼い主からすると「体調がいいのでは?」
と誤解してしまいがち。ですが、実際は
体が常にフルスピードで走り続けている
状態で、確実にダメージが蓄積しています。
甲状腺とは?
甲状腺は首の前側にある
小さな内分泌器官です。
蝶のような形をしており、
普段は外から見えません。
しかし体にとっては大切な
ホルモンを作り出す工場で、
健康維持に欠かせません。
分泌されるホルモンは
T4(サイロキシン) と
T3(トリヨードサイロニン)。
これらは代謝をコントロールし、
食べ物から得た栄養をどの程度
エネルギーとして燃やすかを
調整しています。
猫にとっては、体温の維持、
心拍数の調整、筋肉や脳の働き、
さらには毛並みや皮膚の健康に
まで影響を及ぼします。
つまり、甲状腺は「体のエンジン」
のスイッチ役なのです。
ただしこのホルモンが過剰に出ると
エネルギーを使いすぎてしまい、
体重が減ったり心臓に負担が
かかったりします。
これが猫に多い
「甲状腺機能亢進症」です。
人間にも同様の病気が存在します。
バセドウ病(Basedow病) は
甲状腺ホルモンが過剰に分泌され、
動悸、発汗、体重減少などを
引き起こす病気です。
一方、ホルモンが不足する
橋本病(慢性甲状腺炎) は
疲労感やむくみ、体重増加などの
症状を招きます。
猫ではホルモン不足の病気は稀で、
むしろ過剰になるタイプが
圧倒的に多いのが特徴です。
これは加齢に伴う細胞変化や
腫瘍性の増殖が関係していると
考えられています。
人と猫の違いはありますが、
どちらにとっても甲状腺は
全身のエネルギーを司る要の臓器。
その働きが乱れると健康全体に
影響が及ぶため、定期的な検査や
早期発見が重要となります。

甲状腺機能亢進症とは?
主に10歳以上で発症し、
多くは甲状腺の良性の
「腺腫様過形成」により
ホルモンが過剰になる病気。
ホルモン過剰で基礎代謝が上がり、
心拍と血圧が上昇、体温維持に
エネルギーを使いすぎます。
腸の動きが活発になり、嘔吐や
軟便が増える子もいます。
典型症状は、多食と体重減少、
多飲多尿、落ち着きの低下、
夜間の活動増加、被毛の艶低下、
鳴き声の変化など。
一見「若返った」ように見えるのが
落とし穴です。
診断は触診での甲状腺腫大の確認、
血液検査で総T4高値をチェック。
境界値なら遊離T4やTSH測定、
超音波やシンチで評価します。
高血圧や心雑音の有無も重要です。
腎臓との関係も要注意。
亢進症で代謝が高い間は腎機能の
低下が隠れることがあり、治療で
代謝が下がると腎不全が顕在化する
ケースがあります。
治療開始後は腎機能の同時評価が
欠かせません。
治療選択肢は主に四つ。
①抗甲状腺薬(メチマゾール等)
内服や外用でホルモン合成を抑制。
定期的な血液検査で副作用を確認。
②放射性ヨウ素治療(I-131)
根治性が高く再発が少ない方法。
③外科的切除
適応と全身状態を見て選択。
④ヨウ素制限食
単独または補助療法として使用。
どの方法でも、血圧、体重、心機能、
腎機能、T4値を定期的にモニタリング。
適切に管理できれば、生活の質は
大きく改善し、長く穏やかに暮らせます。

代謝が上がる=元気に見えるけど…
「元気すぎる」状態は健康とは限りません。
・心臓に負担がかかり不整脈や心不全に
発展する可能性
・腎臓機能の低下を早める
・高血圧から網膜剥離など眼の病気に進む
ことも
こうした合併症が命に直結することがあり、
早期発見が何よりも大切なのです。

見た目に騙されないで!
「よく食べているし、まだまだ
元気だから大丈夫!」と感じるのは
飼い主さんとして自然なことです。
しかし、甲状腺機能亢進症と同じく
高齢猫に多い病気の多くは、
一見すると元気そうに見えるため、
発見が遅れやすいのが特徴です。
例えば 慢性腎臓病。
シニア猫の約3~4割が発症すると
言われるほど身近な病気ですが、
初期は「よく水を飲む」「おしっこ
の量が増えた」といった小さな変化
しか現れません。飼い主さんにとっ
ては「健康的に水分補給してる」
ように見えてしまうのです。
また、糖尿病も注意が必要です。
こちらも「よく食べるのに痩せる」
という症状が出るため、甲状腺機能
亢進症と混同されることがあります。
食欲旺盛で活動的に見えても、
体は確実に負担を抱えているケース
があるのです。
さらに、心臓病や高血圧も
外見だけでは判断が難しい代表例。
元気に走り回っているようでも、
心臓に負担がかかり続けていたり、
血圧が高いまま放置されていること
があります。
このように「まだ元気だから」と
油断してしまうのが、シニア期の
健康管理における大きな落とし穴。
見た目の元気さは必ずしも健康の
証ではないと知っておくことが
とても大切です。
だからこそ、定期的な健康診断や
日常の細やかな観察が重要になり
ます。甲状腺だけでなく腎臓や血糖、
心臓などを同時にチェックすることで
早期発見につながり、治療の選択肢
を広げることができます。

早期発見のカギは“いつもと違う元気”
甲状腺機能亢進症は、早期に見つければ
内科治療や食事療法でコントロールが
可能です。
・定期健診(血液検査で発見できる)
・体重の推移を記録する
・食欲や鳴き声の変化を観察する
特に「なんだか最近元気すぎるかも」と
感じたら、迷わず動物病院で相談を。
愛猫の小さな異変を見逃さないことが、
健康寿命を延ばす第一歩です。

高齢猫に多い甲状腺機能亢進症は、
「よく食べているのに痩せる」
「若返ったように元気になる」など、
一見うれしい変化に見える症状を
伴うことが多いため、発見が遅れる
ケースが少なくありません。
しかし、代謝の暴走は心臓や腎臓へ
深刻な負担を与え、放置すれば命に
関わる病気です。見た目の元気さに
惑わされず、小さな異変を見逃さず
に気づくことが最大の予防策です。
特に10歳を過ぎた猫では、年に一度
の健康診断を欠かさないことが重要。
血液検査で甲状腺ホルモンを測定す
ることで、初期段階で異常を察知し
やすくなります。さらに体重の変化
や飲水量、排泄回数、夜間の活動な
どを日頃から観察・記録しておけば
診察時に役立ちます。
治療法には薬、放射性ヨウ素治療、
手術、療法食など選択肢があり、
猫の年齢や体調、家庭環境に合わせ
て最適なものが選ばれます。治療を
始めた後も腎臓や心臓の状態を同時
に見守ることが大切です。
甲状腺機能亢進症は早期発見・適切
な治療で十分にコントロール可能な
病気です。「ただの老化」や
「元気なだけ」と思わず、気になる
サインがあれば迷わず動物病院に相
談することが、愛猫の健康寿命を延
ばす大きな一歩となります。



