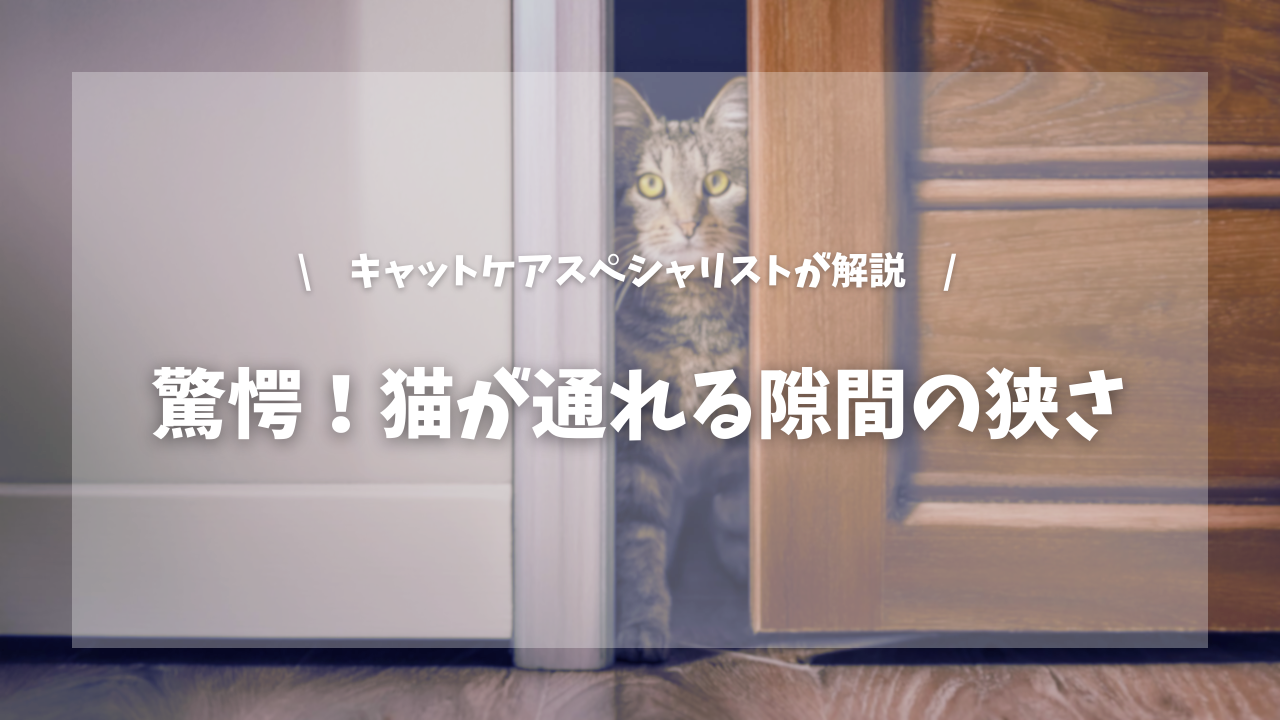
驚くような狭い場所を通って脱走してしまう猫。
液体といわれるぐらい体が柔軟な
猫は、いったいどの狭さまで通り抜ける
ことができるのか?
危険な隙間に対処して脱走防止を強化しよう!
家の中なのに猫の姿が見あたらない。
思いあたるところを探しても
どこにもいない…
「え?もしかして、脱走?」
焦る気持ちをおさえながら
もう一度ゆっくり探してみる。
「あれ?こんなところにいたの?」
と驚くような場所で猫が寝ていた
経験はありませんか?
猫はかくれんぼの天才で、
私たちの想像をはるかに超えます。
思いもよらない場所にいるということは、
思いもよらない隙間や入り口が
存在しているということです。
その隙間の先が猫にとって安全か
どうかはわかりません。
私たちが気づかないうちに
猫を隙間に閉じ込めてしまうこともあります。
あるいは「ここなら大丈夫」と
過信してしまい、脱走を許すことも。
猫の安全のため、隙間対策を
今一度考えてみましょう。

猫が通れる隙間ってどのくらい?
猫はどんな狭い場所でも通れる
イメージがありますが、実際には
どれくらいの隙間を通れるのでしょうか?
猫は頭が通ればすり抜けられる
隙間を見つけた猫はまず、
自分の頭が入るか確認します。
頭が通ってしまえばスルッと通過可能です。
なで肩で知られる猫は肩幅がほとんどなく、
頭が通れば体も問題なく通り抜けます。
猫の柔軟な体は、
私たちの想像を超える狭さに対応できます。
猫の頭は何cm?
個体差はありますが、
成猫の頭幅は
約6cmといわれています。
縦幅は横幅より薄くなるので、
横に向ければさらに狭い隙間も通れます。
子猫の場合はさらに小さく、
顔の横幅は3~4cm程度。
小さい子猫なら、ほんの少しの隙間も
通り抜けることが可能です。
6㎝の身近なもの
6㎝と言われてもあまりピンとこない
かもしれません。しかし、身近なものに
例えてみると、その狭さに驚くはずです。
- トランプの横幅
- レシートの横幅
- 単一電池の高さ
-
500mlペットボトルの直径
これらの大きさで、猫が通れると考えると
その狭さに驚くはずです。

猫が通れる隙間を知っていると何に役立つ?
家の中で猫が侵入できる場所がわかる
レシートやトランプを持って、家の中の
隙間を確認してみてください。
ここも通れるのかと驚く結果になると思います。
今までは気にも留めていなかった場所が、
侵入できる場所だと認識することができます。
入って欲しくない場所や、危険な箇所に対策することができるでしょう。
脱走防止の対策を強化することができる
すでに脱走防止の対策をしていても、
通り抜けられる隙間を再確認することで
対策の甘さが見つかるかもしれません。
問題ないと思っていた隙間を
通り抜けられる可能性があると知れば、
さらに対策をとって脱走防止を強化することができます。
猫がより安全に暮らせる
猫は探検家です。ちらっと見える
その隙間の先を冒険したくなります。
隙間の先に危険が待っているとしたら、
中に入ってほしくはありません。
危険な隙間に対策をたてることは、
猫たちがより安全に暮らせることにも繋がります。

限界に挑戦!うちの子はこの狭さを通れる?
私たち人間にも個人差があるように、
猫にも個体差があります。
標準の大きさや通れる隙間の目安が
あっても、一緒に暮らしているうちの子
が通れるとも限りません。
引き戸を使ってどこまでの隙間を通れるか確認してみましょう。
1|まずは10㎝の隙間から挑戦
引き戸の隙間を10㎝にあけておき、
おもちゃやおやつで隙間を通るように誘います。
2|徐々に隙間を狭くしていく
いっきに間隔を狭くするのではなく、
徐々に隙間を狭くしていきます。
3|通れなかった隙間がその猫の限界
頭を入れたけど通れず戻るなど、
完全にからだのすべてが通れない幅が
うちの子の基準の狭さになります。
※注意点
引き戸が動くと正しく測れないので、
動かないように固定すること。
実際に挑戦してみると、通れる隙間の狭さに驚きます。
私たちが想像していた幅より狭い隙間を通ってしまうのです。

日常生活での隙間対策
家具と壁の隙間
家具の下や壁の隙間は、猫が
隠れたり通ったりする場所です。
隙間に板やストッパーを設置して
侵入を防ぎましょう。
電化製品周り
コードの間や家電の下も危険です。
隙間から抜けられないよう
配線カバーやボードで対策を。
ドアの下の隙間
ドア下の少しの隙間も猫は通れます。
段ボールや専用ストッパーで封鎖することで
脱走や誤飲事故のリスクを下げられます。
玄関や窓の注意点
玄関や窓は脱走が最も多い場所です。
ドアを開ける一瞬や、網戸のわずかな隙間から
猫は外に出てしまうことがあります。
-
玄関は柵やストッパーを活用
-
窓や網戸はロックやネットを設置
-
高層階のベランダも油断せず、
脱走防止ネットを張る
これらの対策は命を守るために重要です。
キャリーバッグの注意点
ファスナータイプのソフトキャリーは
猫が必死に脱出する可能性があります。
ハードタイプや首輪に引っかけられる
タイプに変えると安全です。
旅行や通院時の脱走事故も
防ぐことができます。
脱走が起こりやすい状況
猫はいつでも好奇心旺盛です。
特に以下のような状況で、脱走のリスクが高まります。
-
掃除や模様替えで家の出入りが増えた時
-
来客があり玄関ドアを頻繁に開け閉めする時
-
室内で大きな音や物音がした時
-
窓や網戸が少し開いている時
こうした瞬間に猫はチャンスと見て、
わずかな隙間から外に出ようとします。
家の中で油断していると、猫は予想外の行動を
とることがあります。
脱走防止グッズの活用
市販や手作りで脱走防止対策が可能です。
例えば以下のようなグッズがあります。
-
玄関用のペットゲート
-
網戸ロックや補強ネット
-
ドア下用のストッパーや段ボール板
-
キャリーバッグやケージのファスナー補強
-
高さ調整可能なフェンスや仕切り
簡単なDIYでも十分役立ちます。
段ボールや板を使い、猫が通れない通路を作るだけで
脱走リスクは大幅に減ります。
猫の心理と好奇心
猫は好奇心が強く、
見えない場所に興味を持ちます。
隙間や影、微かな動きに反応し、
探検行動を始めます。
-
物音がした方へ飛びつく
-
小さな隙間に顔を突っ込む
-
知らない空間を探索する
こうした行動は猫の本能ですが、
安全ではない場所に入り込む危険も伴います。
好奇心を満たしつつ安全を確保する工夫が必要です。
脱走が引き起こすリスク
脱走によるリスクは多岐に渡ります。
-
交通事故の危険
-
他の動物とのトラブル
-
感染症や寄生虫への曝露
-
行方不明による飼い主の精神的負担
これらのリスクは、ちょっとした隙間からでも
起こり得ることを意識しておく必要があります。
家の中での安全ゾーン作り
猫に安心して過ごせるゾーンを作ることも大切です。
-
キャットタワーやベッドを複数配置
-
高さや隠れ家を組み合わせる
-
おもちゃで注意を引き、危険区域から遠ざける
安全ゾーンを作ることで、
猫の好奇心を満たしつつ脱走防止にもつながります。
日常でできる小さな工夫
毎日の生活の中で、ちょっとした工夫も効果的です。
-
ドアを開ける時は猫の動きを確認
-
網戸や窓はロックを必ず確認
-
来客時はケージやゲートで一時隔離
-
掃除中の物の配置に注意する
こうした小さな習慣が、脱走リスクを
大幅に下げることにつながります。
脱走が起こりやすい状況
猫はいつでも好奇心旺盛です。
特に以下のような状況で、脱走のリスクが高まります。
-
掃除や模様替えで家の出入りが増えた時
-
来客があり玄関ドアを頻繁に開け閉めする時
-
室内で大きな音や物音がした時
-
窓や網戸が少し開いている時
こうした瞬間に猫はチャンスと見て、
わずかな隙間から外に出ようとします。
家の中で油断していると、猫は予想外の行動を
とることがあります。
まとめ
猫は柔軟で、まるで液体のような体で
私たちの想像を超える狭い隙間も通ります。
ちょっとした隙間が脱走や事故につながることも。
家具の隙間、電化製品周り、ドア下や窓、
玄関、キャリーバッグなど、猫が通れる場所を
すべて把握して対策を取りましょう。
日常生活で油断せず、常に猫の安全を意識することが、
毎日を安心で楽しいものにしてくれます。
脱走防止の対策をしっかりと行い、
リスクを減らすことで、猫との幸せな時間を守りましょう。
猫と一緒に暮らす上で、
隙間の存在に気づくことはとても大切です。
思いもよらない場所から脱走してしまう前に、
安全な家づくりをしてあげてください。



