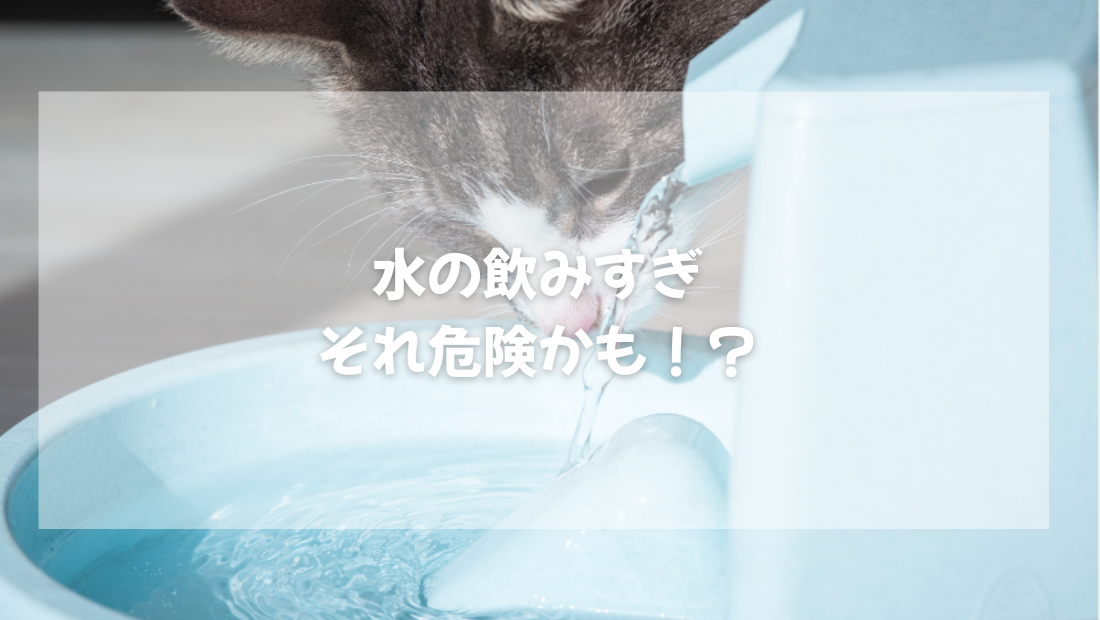
猫は本来あまり水を飲まない動物です。だからこそ「水を飲みすぎる」「おしっこが増える」といった変化は体からのSOSの可能性があります。慢性腎臓病、糖尿病、甲状腺機能亢進症などの病気が隠れていることも少なくありません。日々の飲水量やトイレの様子を観察・記録し、気になるサインがあれば早めに動物病院へ相談を。小さな気づきが大切な命を守るカギになります。
水を飲む=元気?
「たくさん水を飲んでいるから
健康そう」そんなふうに
思っていませんか?
実は猫が水を飲みすぎたり、
おしっこを出しすぎる状態は
体からのSOSのサインかも
しれません。
猫はもともと砂漠にルーツを持つ
動物で、犬に比べて水をあまり
飲まない性質があります。
だからこそ
「急に水を飲む量が増えた」
「トイレがやけに濡れている」
といった変化は見逃せない
大切なシグナルです。
さらに厄介なのは、多飲多尿が
始まった時点で、すでに体の中で
病気が進んでいることがある点です。
水を飲む姿は元気に見えるため
安心しがちですが、実際には
「隠れた体調不良」を覆い隠して
いることも少なくありません。
今回は「多飲多尿」と呼ばれる
症状のチェックポイントや、
病気の早期発見につながる観察法を
わかりやすく解説します。
水をよく飲む=健康じゃない!?
猫が水を飲む姿を見ると
「元気で安心」と思いがちです。
しかし水の飲みすぎは、
腎臓やホルモン系の病気が
隠れているサインのことも。
「多飲多尿」という言葉は
獣医療の現場でよく使われます。
たくさん水を飲んで、たくさん
おしっこをする状態のことを
指しています。
本来あまり水を飲まない猫だから
こそ、いつもより増えた飲水量は
要注意なのです。
特にシニア猫では「年のせい」と
見過ごされやすいですが、実際は
腎臓や甲状腺の不調が関わっている
ケースも多いのです。
「元気に水を飲んでいる=健康」
とは限らない、という視点を
持っておきましょう。

「多飲多尿」ってどんな状態?
多飲多尿とは、その名の通り
水を大量に飲み、尿量も増える
状態をいいます。
目安は「体重1kgあたり1日50ml」。
例えば4kgの猫なら200mlが
基準です。これを大幅に上回る
ようなら異常の可能性があります。
また尿の量が明らかに増え、
トイレ掃除をしてもすぐに
砂がぐっしょりしている場合も
サインのひとつです。
飲水量を毎日計測するのは難しい
かもしれませんが、500mlペット
ボトルを基準にして飲んだ量を
記録すると把握しやすくなります。
「いつもの感覚」と比べてどうかを
見るだけでも、早期発見に
つながります。
代表的な病気と多飲多尿の関係
多飲多尿は、単なる癖や年齢の
せいではなく、体に潜む病気の
サインであることが少なく
ありません。代表的な3つの病気を
知っておくことが大切です。
まずは慢性腎臓病です。
腎臓は尿を濃縮する役割を持ちます。
腎機能が落ちると水分を保持できず
薄い尿を大量に出してしまいます。
体は失われた水分を補おうとして
強い喉の渇きを感じ、結果的に
水を多く飲むようになります。
特にシニア猫に多く見られます。
次に糖尿病。
血液中に余分な糖が
増えると、尿と一緒に糖が排泄され、
その際に多くの水分も引き込まれて
しまいます。
これを浸透圧利尿と
呼びます。結果として多尿が起こり、
それを補うために強い多飲が
見られるのです。
そして甲状腺機能亢進症。
代謝が過剰に上がり、体の中で水分や
エネルギーが消費されやすくなります。
その結果、水を飲む量と尿の量が
ともに増えるのが特徴です。
中高齢の猫に発症が多く、体重減少や
活動性の変化も伴うことがあります。
これらの病気はすべて早期発見が
重要です。
多飲多尿という共通した
サインをきっかけに、早めに受診すれ
ば重症化を防げる可能性があります。

こんなことありませんか?①
「お水のお皿がすぐ空になる」
そんな様子が続くときは要注意。
猫が1日に必要とする水分量を
大きく超えている可能性が
あります。
特に若い頃はあまり水を飲まなかっ
たのに、シニア期になって急に
飲む量が増えたときは注意が
必要です。
複数の水飲み場を用意していても
次々空になる、床が濡れているほど
水をこぼして飲んでいる――
こうした変化も多飲のサインです。
毎日の器の減り具合を意識して
観察しましょう。

こんなことありませんか?②
「キッチンやお風呂場で水を
欲しがるようになった」
そんな行動の変化もサインです。
器からの飲水量が足りないときに
新しい水源を探し回ることが
あります。
今まで見られなかった行動なら、
健康状態の変化を疑いましょう。
水道の蛇口から直接飲みたがる、
お風呂の残り湯をしつこく欲しがる
などの行動は、飼い主が見逃しがち
です。これまでなかった水への執着
が見られたら、すぐに記録を残し
ましょう。

こんなことありませんか?③
「トイレの砂がすぐに濡れている」
「掃除してもすぐにぐっしょり」
そんなときは尿量が増えている証拠。
腎臓病や糖尿病では尿を濃縮する
力が弱まり、水のように薄い尿を
大量に排泄することがあります。
トイレの変化は健康の鏡です。
普段から観察する習慣を持ちましょう。
おしっこの塊が以前より明らかに
大きい、掃除の回数が増えたなども
大切な手がかりです。
毎日同じ時間にチェックする習慣が
あれば、些細な変化に気づきやすく
なります。

こんなことありませんか?④
「おしっこの色が前より薄い」
これも要注意ポイントです。
正常な猫の尿は薄いレモン色。
それよりもさらに薄い場合は、
体が水を保持できていない可能性
があります。
尿が薄い=水分が体にとどまらず
出てしまっている状態。
腎臓に負担がかかっているかも
しれません。
また尿の臭いが極端に弱くなった
ときも要注意です。尿の濃縮が
できないことで臭いも薄くなるため
病気のサインになりえます。
色・量・臭いの3点を観察する
ようにしましょう。
病気のサインを見逃さない
多飲多尿は、腎臓病や糖尿病、
甲状腺機能亢進症など、
猫に多い病気のサインです。
特に腎臓病は高齢の猫に多く、
気づかないうちに進行する
サイレントな病気です。
「年齢のせいかな?」と
放置せず、気づいたら
早めに受診することが
愛猫の命を守る第一歩です。
定期健診で血液検査や尿検査を
受けることも大切です。
年1回の健康診断に加え、
シニア期に入ったら半年ごとに
チェックするのが安心です。
まとめ
「水を飲む=元気」と思われがち
ですが、実際には飲みすぎや
おしっこの出しすぎは体からの
SOSであることが少なくありません。
慢性腎臓病や糖尿病、甲状腺機能
亢進症など、多飲多尿の背後には
深刻な病気が隠れている可能性が
あります。しかもこれらは猫に
多く見られる病気であり、放置すると
命に関わることもあります。
しかし逆にいえば、飼い主が早く
気づき、動物病院に相談できれば
病気の進行を遅らせたり、生活の
質を保ちながら過ごせる可能性も
大きくなります。
だからこそ日常の観察が重要です。
水のお皿の減り具合、トイレの砂の
状態、おしっこの色や臭い…。
小さな変化を見逃さない習慣こそが
愛猫の健康を守る第一歩なのです。
観察に加えて、記録も大切です。
飲水量をメモする、尿の写真を撮る、
動画で行動を残す。これらは診察時に
獣医師が診断するうえで大変役立つ
「客観的な情報」となります。
「年齢のせいかな」と思わずに、
「いつもと違うかも」と感じた時点で
動物病院に相談してみましょう。
早期発見・早期治療が愛猫の未来を
大きく左右します。
多飲多尿は、飼い主が最も気づき
やすい異変のひとつです。
だからこそ、気づけるかどうかが
愛猫の健康寿命を延ばすカギに
なります。
今日から少しだけ、水やトイレの
チェックに目を向けてみませんか。
その小さな一歩が、大切な家族の
命を守る大きな力となります。





