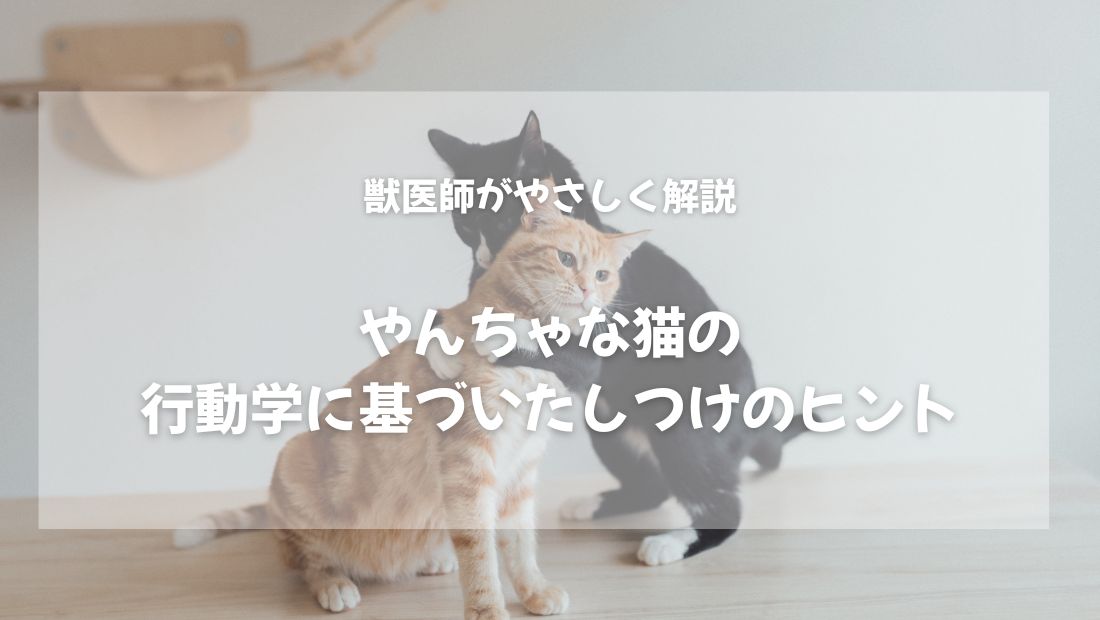
元気すぎる猫の行動に悩んでいませんか?
飛びつき、甘噛み、夜の運動会…そのやんちゃは“困った”ではなく、健やかな成長の証かもしれません。
獣医師の視点から、叱らずにのびのび育てるための環境づくりやしつけのコツをやさしく解説します。
「やんちゃすぎる猫」に
困っていませんか?
行動学に基づいた
しつけのヒント
「カーテンをよじ登る」
「家具の上からダイブする」
「夜中に大運動会」――
猫と暮らし始めて、
そんな“やんちゃ”な行動に
驚いたり、
ちょっと困った経験は
ありませんか?
とくに子猫や若い猫は
エネルギーに満ちていて、
私たちの予想を
軽く超えるような
行動を見せることもあります。
でも実は、
こうした「やんちゃ」こそ、
猫が本来もっている
自然な本能のあらわれ。
決して悪いことではなく、
むしろ健やかな成長のサイン
とも言えるのです。
「ダメって言ってるのにやめてくれない…」
「叱ってもまた同じことをする」
そんな風に感じたことが
ある方も多いのでは
ないでしょうか。
実は猫にとって、
「叱られてもなぜ叱られたのかを理解する」
のは難しいこと。
犬のように飼い主の指示に
反応するタイプではなく、
猫はより「環境」に
強く影響される動物なのです。
だからこそ、
叱るよりも
“行動が起きないように環境を整える”
ことが、
猫と快適に暮らすための
第一歩になるのです。
今回は、
獣医師としての視点から、
やんちゃすぎる猫との
上手な向き合い方を
行動学の観点でご紹介します。
無理に叱ったり
押さえつけたりせず、
猫がのびのびと暮らせる環境を
整えてあげるためのヒントを、
やさしく解説していきます。
1. 「うちの子、やんちゃすぎる…」
は自然なこと

猫は本来、
とても好奇心旺盛で
活発な動物です。
特に1歳未満の子猫や、
2〜3歳頃までの若い猫は、
体も心も成長の真っ最中。
毎日が刺激と発見の連続で、
遊びやいたずらも
どんどんパワーアップしていきます。
たとえば、
家具に飛び乗ったり、
壁を駆け上がったり、
手や足に飛びついて
甘噛みしてきたり…。
こうした行動はすべて、
「遊びたい!」
「構ってほしい!」
「何かしたい!」
という気持ちのあらわれです。
特に子猫の場合、
本来であれば
兄弟猫や母猫と過ごす中で、
「どこまでやると痛いか」
「相手が嫌がるか」
といった
“社会的なルール”を学びます。
しかし、
生後2〜3か月頃の社会化期に
人間の家庭に迎えられると、
こうした経験が不足しやすく、
「ひとり遊び」が
過剰になってしまうことがあります。
それが、
「激しい甘噛み」や
「手足への飛びつき」
といった行動に現れるのです。
2. 静かな猫が“いい子”
ではない理由
「静かに寝てばかりいる猫は
手がかからなくていい子」
そんなふうに感じたことが
ある方もいるかもしれません。
でも実は、
猫にとって
“やんちゃに動ける環境”
こそが自然で、
健康な状態とも言えるのです。
猫は、
動く・登る・隠れる・狩る――
といった本能を持つ生き物。
それらの行動が
満たされていないと、
ストレスがたまり、
体調を崩すきっかけに
なってしまうこともあります。
「静かな猫=理想的」
ではなく、
適度にやんちゃができる環境を
整えてあげること。
それが、
猫の心と体のバランスを
保つうえで
とても大切な視点なのです。
また、
猫の活発さには
年齢による変化もあります。
一般的に、
猫は3歳くらいまでは
とても活発ですが、
それ以降は
精神的な落ち着きが
見られるようになります。
中には、
4〜6歳くらいまで
元気いっぱいのまま
過ごす子もいれば、
2歳を過ぎた頃から
穏やかになる子もいます。
成長のペースにも
個性があるのです。
私自身も、
多くの猫ちゃんとご家族を
見てきた中で、
「3歳を過ぎて急におとなしくなった」
「落ち着いてきたタイミングで2匹目を迎えました」
といったご相談を
よく耳にしてきました。
“やんちゃな時期”は永遠ではありません。
だからこそ、
その貴重な期間を
ポジティブに捉え、
上手に付き合っていくことが
大切です。
3. 「叱る」より「整える」
行動学的なしつけの考え方

やんちゃな行動が続くと、
つい「ダメ!」と
叱りたくなるものです。
ですが、
猫は「叱って理解する」ことが
あまり得意ではありません。
猫の行動を変えるために
有効なのは、
「その行動をしなくてもよい環境をつくること」。
つまり、
欲求を“適切に発散できる場所や方法”
を用意することで、
問題行動を自然と減らすという考え方です。
たとえば――
- 高いところに登るのが好き
→ キャットタワーや棚を活用して
“登ってもいい場所”を増やす - 甘噛みが激しい
→ 噛んでもOKなおもちゃを
与えて発散させる - 夜中に走り回る
→ 日中の遊び時間をしっかり確保することで、
夜はぐっすり眠れるように
こうした「行動の代替」を行うことで、
叱らずとも
猫は自然と行動を切り替えていきます。
“やってほしくない行動”
の裏には、
必ず
“満たされていない欲求”が
あるのです。
4. マンネリ防止がカギ!
刺激と遊びに「変化」を
どんなに
良い環境やアイテムを用意しても、
猫は意外と飽きやすい動物。
お気に入りだった
キャットタワーやおもちゃも、
次第に
使わなくなってしまうことが
あります。
だからこそ、
定期的に環境を見直すことが
大切です。
たとえば――
- キャットタワーの位置を変える
- 隠れ家に布をかけて模様替えする
- しばらくしまっておいたおもちゃを“再登場”させる
- 窓辺や高い場所を使ってレイアウトに変化をつける
こうしたちょっとした工夫で、
「また新しい冒険が始まった」
と猫は喜び、
自然に活動量が増えます。
やんちゃな行動を“禁止する”のではなく、
“やんちゃが発揮できる新鮮な環境”をつくる。
それが、
猫の心と体を健康に保つ
ポイントです。
5. 飼い主の反応が
やんちゃを助長することも
意外かもしれませんが、
やんちゃな行動が続く理由の
ひとつに、
飼い主のリアクションが
あることも。
たとえば、
甘噛みに対して
大きな声を出したり、
手を振り払ったりすると、
猫にとっては
「構ってもらえた!」
というごほうびに
なってしまうことがあります。
猫は
「注目される」
「反応がある」と、
行動を強化してしまう
傾向があります。
つまり、
やんちゃな行動に
過剰に反応すると、
それが
繰り返されやすくなるのです。
理想的なのは、
「落ち着いた反応」と
「意味のないリアクションをしない」
こと。
反応せずにスッと離れる、
他の遊びに切り替えるなど、
猫の行動に
振り回されすぎない対応が
有効です。
番外編
やんちゃ期にできる
“ちょっとした工夫”
と心の余裕

子猫や若い猫が元気すぎて困る…
そんなときに役立つのが、
日々のちょっとした工夫と
「飼い主側の心の余裕」です。
たとえば、
毎日10分でも
集中して遊ぶ時間をつくることで、
猫のストレスや退屈は
大きく軽減されます。
短い時間でも、
猫にとっては満足感のある
大切なコミュニケーションの
ひとときになるのです。
また、やんちゃな時期には
「どこまでやったら怒られるのか」
を試すような行動も
見られることがあります。
そんなときこそ、
叱るよりも“切り替える”こと。
気になる行動を見たら、
別のおもちゃや場所に誘導して、
「こっちで遊ぼうね」と
導いてあげることで、
猫は無理なく学んでいきます。
やんちゃすぎて
手がかかる時期を過ぎると、
「あの頃の元気さが懐かしい」
と感じる方も多いものです。
そのタイミングで、
2匹目の迎え入れを検討される方も
いらっしゃいます。
多頭飼いを考える際は、
年齢差や性格の相性、
生活スペースの確保なども
大切な要素です。
新しい家族を迎えることで、
先住猫のやんちゃが
落ち着いたり、
逆に刺激をもらって活発になる
ケースもあります。
「手がかかる時期=困る時期」
ではなく、
猫が健やかに育っている証
として受けとめ、
必要以上に自分を責めすぎずに
過ごしていただけたらと思います。
まとめ
「やんちゃ」は猫らしさ。
上手につきあえば
もっと仲良くなれる
猫の“やんちゃすぎる行動”に
悩むことは、
決して特別なことではありません。
むしろそれは、
猫が元気で、
好奇心をもって暮らしている証でもあります。
「うちの子、なんでこんなに落ち着かないの?」
と悩んだときこそ、
その行動の裏にある
気持ちや本能に
目を向けてみてください。
そして、叱るより、
猫が安心して
本能を発揮できる環境を
整えてあげること。
やんちゃな時期は、
あっという間に
過ぎてしまいます。
後になって振り返ったとき、
「あの頃、本当に元気だったなあ」
「手がかかったけど、かわいかったな」と、
きっと懐かしく、
大切な思い出に
なっているはずです。
猫の成長とともに
変化する日常を、
ぜひ前向きに、
温かく楽しんでくださいね。



