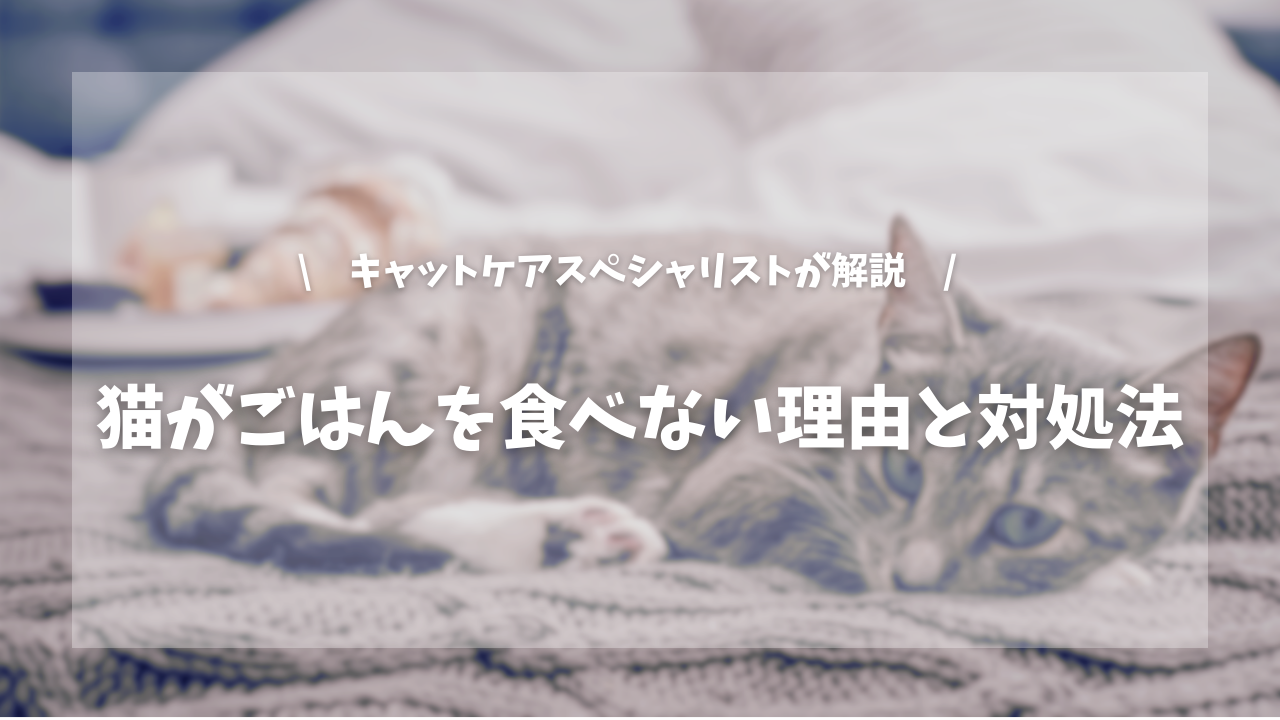
猫がごはんを食べてくれない。
食べない理由を理解して、
またもぐもぐ食べてくれるような
アイデアをキャットケアスペシャリストが提案します!
猫がごはんを食べなくなるのは何が原因
なのか?猫はどうやって好きなごはんを
決めているのか?それがわかれば
しっかりごはんを食べてくれる工夫が
できます。
ごはんを食べないからおやつばかり
食べていても、十分な栄養が摂れません。
猫たちが健康に暮らせるように、
もりもりごはんを食べてもらいましょう。
猫がごはんを食べなくなると、
「どこか悪いのでは?」と心配になります。
しかし、猫にとって“食べない”は
さまざまなサインのひとつ。
必ずしも病気だけが原因ではありません。
たとえば環境の変化、
同居猫との関係、季節の移り変わり、
私たち飼い主の生活リズムの変化など、
ほんの少しの出来事が猫の食欲を
左右することもあります。
猫は環境にとても敏感です。
わたしたちが「いつも通り」と感じる
小さな変化でも、猫にとっては
「何か違う」と不安を感じることがあります。
食べない理由を見極めるためには、
“いつから食べなくなったか”“どのくらいの
量を残しているか”を冷静に観察すること。
そして焦らず、猫のペースに合わせて
少しずつ工夫してあげることが大切です。
猫が安心して食べられる環境を整えること、
嗅覚や好みに合わせたフードを選ぶこと、
ストレスを減らすこと。
どれも“食べない”を改善するための
第一歩になります。
「昨日は食べたのに今日は残した」
という日もあるでしょう。
それは猫にとって自然なことです。
大切なのは、“全く食べない日が続く”
ときに、きちんと原因を見つけること。
それが健康を守る最も確実な方法です。

なぜごはんを食べなくなるのか?
猫がごはんを食べなくなる理由は
いくつか考えられます。
ごはんを食べない原因を考えましょう。
1|偏食やいつものごはんに飽きた
猫は嗜好性が高く、好き嫌いが
はっきりしています。
ごはんに飽きた場合、匂いの変化や
食感の違いを好む傾向もあります。
ドライフードを少し砕いて食感を変えたり、
ウェットフードを混ぜて香りを
プラスしてみるのも有効です。
また、容器を変えるだけでも
気分が変わることがあります。
深すぎる器はヒゲが当たって
ストレスを感じる猫もいるため、
平らな食器に変えるのもおすすめです。
2|ストレス
猫は変化を嫌う生き物です。
来客や引っ越し、工事の音など
小さな刺激でも食欲が落ちることがあります。
多頭飼いの場合、順位争いや
相性のストレスも要因です。
ストレスを感じたときは、
安心できる場所に隠れる猫が多いです。
無理に呼び出すより、
落ち着く環境を整えるほうが効果的。
静かな部屋やフェロモンスプレーの使用も
気持ちを安定させる助けになります。
3|発情期
発情期の猫は食事よりも
本能的な行動に意識が向きます。
食べるより外に出たがる、鳴き声が増えるなど、
行動にも変化が見られます。
特にオス猫は外への関心が強まり、
ごはんに集中できなくなります。
発情期が終われば自然に
食欲が戻ることも多いですが、
長期的に続く場合は体力の低下を
招くこともあるため、
早めに去勢・避妊手術を検討しましょう。
4|老化
高齢になると嗅覚や味覚も衰え、
「匂いがしないから食べない」
というケースもあります。
フードを軽く温めて香りを立てたり、
柔らかい食事に変えることで改善します。
また、歯や歯茎のトラブルも
食欲低下の原因です。
食べたそうにしても残す場合は、
口内炎や歯石の可能性もあります。
定期的な歯科ケアや病院での
チェックを取り入れましょう。
5|病気
急に食べなくなったときは、
病気のサインである可能性が高いです。
腎臓病、肝臓疾患、口内炎、感染症など、
食欲低下を引き起こす要因は様々。
元気がなく、隠れる・動かない・
水を飲まないなどの症状を
併発しているときは、
すぐに動物病院へ。
食べない状態が48時間以上続くと、
肝リピドーシス(脂肪肝)という
命に関わる病気になる可能性もあります。
猫はどうやってごはんの好き嫌いを決める?
猫がごはんの好き嫌いを決めるのは
「匂い」です。猫の味覚は
苦味・酸味・塩味の3つといわれています。
甘みやうまみはあまり感じられない
ようです。そもそも味を感じることが
できる味蕾の数も少ないです。
そのため、猫はごはんの味より匂いに
敏感です。嫌いな匂いのごはんは
食べようとしません。猫が好きな匂いを
見つけてあげることが大切です。
猫の嗅覚は人間の約10万倍といわれ、
ごはんの鮮度や油の酸化具合まで
感じ取ります。古くなったフードや
酸化した油の匂いを嫌がる猫も多いです。
開封から時間が経ったフードを残すのは、
わがままではなく“変化に気づいている”
証拠でもあります。特にウェットフードは
酸化が早いため、小分けにして与えると
新鮮さを保てます。
また、過去の経験も影響します。
体調が悪いときに食べたフードを
「食べたら気持ち悪くなった」と
記憶して嫌うこともあります。
そのため、食欲不振の時期に
無理に新しいごはんを与えるのは
逆効果になる場合があります。
さらに、感情の影響も大きいです。
不安や緊張のある環境では、
本来好きなごはんも食べられません。
静かで安心できる場所で食べられるよう、
落ち着いた空間づくりも大切です。
ごはんの好みは、匂い・食感・経験・
環境の4つの要素で決まるといっても
過言ではありません。
猫にとって“おいしい”とは、
味そのものより“安心して食べられるか”
が大きな判断基準なのです。

猫がごはんをしっかりたべる工夫
栄養がしっかり摂れて、飽きないごはんの
あげ方を工夫してみましょう。ベースの
ごはんをコロコロ変えるのではなく、
いつものごはんに少し変化を加えてあげます。
1|トッピング
いつものごはんの匂いに飽きてしまって
いるとしたら、匂いに変化を加えて
あげましょう。「味変」ならぬ「匂い変」です。
ペースト状のおやつをのせるのはおすすめ
できません。猫用のふりかけや少量の
かつおぶし、小魚を砕いたものなどを
ごはんにまぜてあげます。
猫のお気に入りのおやつを砕いて
少し混ぜてあげるのも効果的です。
トッピングはあくまで“香りづけ”が目的です。
量が多すぎると主食を食べなくなる
ことがあるため、香りが立つ程度に
とどめましょう。
2|ごはんをあたためる
ドライフードをあたためる?と思う人
もいるでしょう。ドライフードでも
トースターやレンジなどで少しあたためて
あげることで匂いが増します。
いつものごはんと変わらないのに、
食いつきが戻ることがあります。
あたため過ぎに注意してあげましょう。
さらに、ウェットフードの場合も
軽く温めることで香りが立ち、
食欲を刺激できます。
冷たいままだと匂いが弱く感じるため、
特に冬場は常温以上を意識しましょう。
3|遊びを増やす
そもそも、それほどお腹が空いていない
場合も考えられます。直接ごはんに
工夫しなくても、遊びで運動量を増やす
ことも効果的です。
腹ペコになればいつもよりごはんを
食べるようになるかもしれません。
また、食前に軽い遊びを取り入れると、
“狩りをして食べる”という本能的な流れが
でき、自然に食欲が湧くようになります。
4|おやつを減らす
かわいい猫たちにせがまれて、おやつを
おいしそうに食べている姿をみれば、
ついついおやつの回数が増えてしまいます。
そこを我慢して、おやつの回数を減らし
ましょう。おやつでお腹が満たされる
からごはんを食べなくなります。
また、与えるおやつは総カロリーの
10%以内を目安にしましょう。
カロリーオーバーは肥満や糖尿病の
原因にもなります。
5|ごはんを食べる場所を変える
いつものごはんでも場所を変えるだけで
食べるようになることがあります。
多頭飼いで同じごはんが入っているのに、
自分の皿以外をもぐもぐ食べたりします。
気分転換のためにごはんを食べる場所を
変えてみるのもいいかもしれません。
さらに、静かで落ち着いた場所を選ぶことも
大切です。家族の動線や家電の音などが
少ない場所を選ぶと、食事に集中しやすくなります。

まとめ
ごはんを食べなくなった原因がわからず、
いろんなごはんを試してコロコロ変えて
いませんか?
ごはんを変えなくても、すこし工夫を
するだけで改善できるかもしれません。
また、食べない原因をしっかり考えて
みることで解決することもあります。
ごはんをしっかり食べて健康に
暮らせるように、大きな変化より
小さな工夫から試してみましょう。
猫がごはんを食べないとき、
飼い主としては焦りや不安を感じますが、
一番大切なのは「観察」と「待つ姿勢」です。
猫のペースを尊重しながら、
“食べたいと思える環境”を
整えてあげることがポイントです。
ごはんの種類を変えるよりも、
食事の場所・時間・温度・匂いといった
“食べ方”を見直してみましょう。
ほんの小さな変化で食欲が戻ることもあります。
また、日頃から猫の体調を
把握しておくことも大切です。
食欲だけでなく、水を飲む量や排泄の状態、
毛づくろいの頻度などを見ておくと、
不調の早期発見につながります。
もしどうしても食べない日が続く場合は、
自己判断せず動物病院へ相談を。
病気を早期に見つけることで、
大きなトラブルを防げます。
猫が食べることは、生きることそのものです。
その一口を安心して食べられるように、
今日からできる小さな工夫を積み重ねていきましょう。
それが猫の「幸せなごはん時間」を
守るいちばんの秘訣です。



