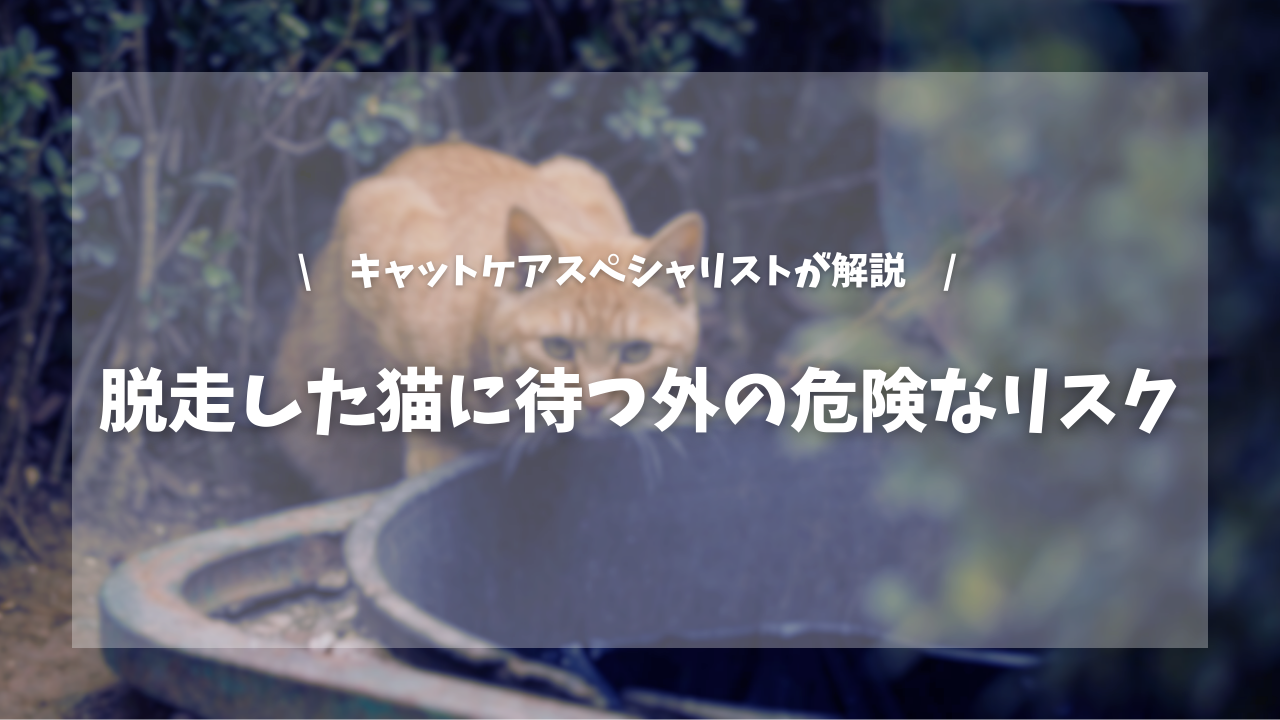
外の危険を知らない猫は、
興味本位で脱走してしまいます。
外の危険なリスクを知ることで、
脱走防止がいかに重要なこと
なのかをキャットケアスペシャリストが解説します。
猫にとって外で暮らすことは
過酷で危険なリスクを伴います。
外で暮らした経験のない猫は、
外がどんなに危険かを知りません。
元野良猫など外で暮らした経験のある
猫は、食べ物や環境などの過酷さは
わかっていたとしても、感染症などの
リスクまで理解しているとはいえません。
外への興味や未練などがきっかけで
脱走してしまう猫。外の危険なリスクを
私たちがしっかり認識して、脱走防止に
努めましょう。

外の世界の危険なリスク
猫が外に出てしまうと、私たちが猫を
危険から守ってあげることはできません。
どんな危険があるのかを知っておきましょう。
1|事故
いちばん多く発生してしまう危険です。
急な飛び出しで車やバイクの事故に
巻き込まれてしまいます。
車の事故だけではありません。高い場所
からの落下や、川に流されてしまう
事故も起こる可能性があります。
工事現場や危険な場所に迷い込んで
事故に巻き込まれることもあるでしょう。
空腹のあまり、危険なものを食べてしまう
こともあります。
外の世界はあらゆる事故に遭う可能性が
あります。
2|感染症や病気
外で暮らしている猫との接触も防ぐことは
できません。感染症などがうつる可能性が
あります。
その中でも気をつけたいのが、猫エイズと
猫白血病です。どちらも治療が困難な病気で、
発症すると死に至ることもあります。
ほかにも接触した猫が持っている病気を
もらうこともあるでしょう。
また、ノミ・ダニ、マダニや寄生虫など
の虫がつくことも考えられます。
3|迷子
家の周辺から離れず、隠れているだけ
であれば見つけることもできるかも
しれません。しかし、家の周辺から離れて
しまい、帰ってこれない猫もいます。
外に一度も出たことのない猫や、元野良猫
でも違う場所で保護された土地勘のない猫
などです。
獲物やほかの猫を追いかけているうちに、
知らない場所まで行ってしまうことが
あります。どこにいるのかわからなくなり、
帰ることができなくなります。

危険なリスクに対して対策はできるのか?
万が一脱走してしまった場合でも、
外の危険なリスクを軽減するために
普段から対策できることはあるのでしょうか?
事故に対して
これは、防ぎようがありません。
できることは、なるべく早く見つけて
あげることぐらいでしょうか。
事故はいつ起こるかわかりません。
道路の横断方法や、危険な場所へ
入らないようにと言い聞かせることも
できません。
感染症や病気に対して
ワクチンや薬である程度防ぐことは
可能です。ただし、猫エイズや猫白血病
に対してのワクチンは猫のからだに
負荷がかかるワクチンです。
また、ワクチンを接種していても、
100%安全とも言い切れません。
脱走を想定してこの2つのワクチンを
接種することもおすすめできません。
迷子に対して
GPS機能のついた首輪をつけたり、
マイクロチップを埋め込むなどの対策は
可能です。首輪はスマホで位置を
確認することができます。
しかし、首輪は脱走後に外れてしまうと
機能は役に立ちません。マイクロチップも
誰かが保護して、動物病院や保健所へ
届けてくれれば確認をとることができます。
脱走を防ぐためにできること
1|完全室内飼いを徹底する
外の危険なリスクを避けるためには
完全室内飼いが最も安全です。
窓やドアの開閉時の注意も忘れずに。
2|脱走防止グッズの活用
網戸ロックやキャットドア、二重扉など
を設置して、猫が簡単に外に出られない
環境を作ることも重要です。
3|日々の環境改善
猫が外に興味を持たないように、
家の中で十分な運動や遊びを
与えることが大切です。
新しいキャットタワーや知育玩具で
好奇心を満たしましょう。
4|家族でルールを共有
脱走のリスクを減らすために、家族全員が
ドアの開閉や外出時の注意を守ることが
必要です。
誰かが油断すると脱走の可能性が高まります。
5|脱走時の心構えを持つ
万が一の脱走時に焦らず対応できるよう
日頃から心の準備をしておくことも
飼い主として大切です。
脱走時の具体的対応
1|まず落ち着かせる
猫を発見したら、急に駆け寄ってはいけません。
大声を出さず、静かに距離を取りましょう。
猫が逃げないように、ゆっくりしゃがみ
手を差し出して安心させます。
2|安全な捕獲グッズの活用
キャリーやタオル、ケージなどを用意して
捕まえると安全です。
直接抱き上げるより、落ち着いた環境で
誘導するのがポイントです。
3|食べ物で誘導
ウェットフードやおやつを少しずつ置いて
猫を誘導します。無理に近づくより
食べ物で関心を引く方が安全です。
4|帰宅後の健康チェック
脱走後は必ず体調を確認しましょう。
怪我や外部寄生虫のチェックを行い、
必要であれば動物病院で診察してもらいます。
5|心理的ケアも忘れずに
怖い経験をした猫は、家の中でも
警戒心を強めることがあります。
安心できるスペースや毛布、
隠れられる場所を作ってあげましょう。
6|再発防止の工夫
脱走経路を確認し、再発防止策を強化します。
網戸やドアの固定、窓の施錠などを
徹底しましょう。
7|脱走後の行動観察
捕まえた後は猫の行動を注意深く観察します。
普段と違う鳴き方や食欲の変化、
トイレの異常などを確認しましょう。
異常があれば早めに病院へ。
まとめ
脱走した猫は、家の外で多くの危険にさらされます。
外の世界は、猫にとって未知で過酷な環境です。
車やバイク、建設現場、川や高所など、
事故のリスクは
常に存在しています。
猫は自分で安全を判断できないため、
飼い主がそのリスクを理解し、
防ぐ努力をすることが不可欠です。
外で暮らす猫同士の接触も避けられません。
感染症や寄生虫のリスクがあり、
特に猫エイズや猫白血病は
治療が難しく、
発症すれば命に関わることもあります。
ノミ、ダニ、マダニなどの寄生虫や、細菌感染も
脱走によって増える可能性があります。
迷子になるリスクも大きな問題です。
外に出たことのない猫や、
元野良猫でも知らない場所では
土地勘がなく、
追いかけた獲物や他の猫の影響で
どこにいるのかわからなくなることがあります。
見つけるまでに時間がかかればかかるほど、
事故や病気のリスクは増えてしまいます。
外の危険を完全に防ぐことはできません。
事故は突然起こるため、
避けようがなく、
感染症もワクチンや薬である程度防ぐことは可能ですが、
100%の安全は保証できません。
マイクロチップやGPS付き首輪は
迷子対策として有効ですが、
完璧ではなく、補助的手段にすぎません。
だからこそ、
最も重要な対策は「脱走させないこと」です。
完全室内飼いにすることで、
事故や感染症、迷子のリスクを
大幅に減らすことができます。
窓やドアの開閉、網戸の固定、
二重扉やキャットドア、脱走防止策の利用など、
環境整備を徹底しましょう。
室内でも猫が飽きないように遊びや運動を工夫し、
外への興味を減らすことも大切です。
脱走してしまった場合には、
できるだけ安全に猫を
捕まえる工夫も必要です。
慌てて駆け寄るのではなく、
声をかけながら落ち着いて近づくことで、
事故や怪我を防ぎ、
猫が安心して家に戻れる環境を作ることができます。
猫の安全は飼い主の責任です。
外の危険なリスクを正しく理解し、日頃から脱走防止や
環境整備を行うことで、猫の命と健康を守ることができます。
事故や感染症、迷子など、外のリスクは予測できない部分もありますが、
飼い主ができることを積み重ねることで、被害を最小限に抑えられるのです。
脱走は一瞬の隙から起こります。
だからこそ、
私たち飼い主は常に警戒と対策を怠らず、
安全な暮らしを守ることが求められます。
外の危険にさらされる猫を増やさないために、
脱走防止と日常の注意が、
猫の命を守る最大の方法です。




