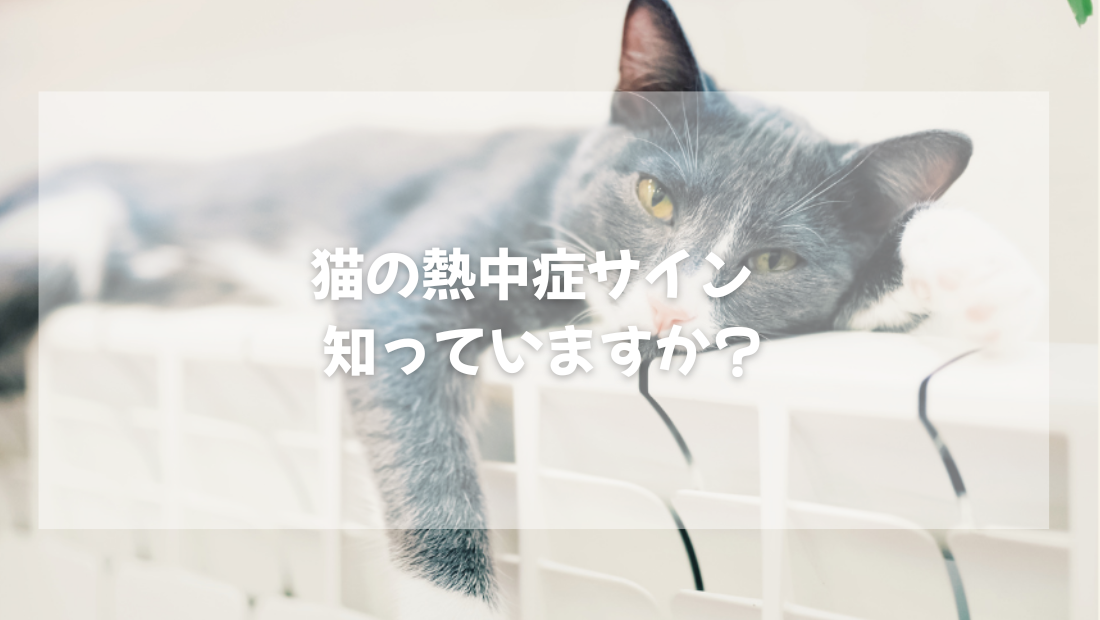
猫は実は暑さに弱く、熱中症は命に関わるとても危険な病気です。舌を出しての呼吸、よだれ、皮膚の戻りの遅れはSOSのサイン。特に短頭種・高齢猫・子猫はリスクが高く、室内でも油断できません。エアコンで28℃以下を保ち、風通しや涼しい場所を複数確保するなど環境づくりが何よりの予防。にゃんガードで安全に移動できる範囲を広げれば、猫自身が快適な場所を選べます。日々の工夫で大切な命を守りましょう。
「猫は暑さに強い」
そんなイメージを持っていませんか?
実はこれは大きな誤解です。
猫は砂漠地帯にルーツを持つ動物で、
水分を効率的に利用できる体の仕組みを
備えています。
そのため、私たち人間のように大量の汗を
かいて体温を調整することができません。
結果として、環境の暑さに
とても弱いのです。
さらに、猫は不調を隠す習性があります。
「元気そうに見えるから大丈夫」と思っても、
実は体は限界に近づいていることも。
気づいたときには重症化しているケースも
少なくありません。
熱中症は命に関わる病気です。
特に高齢猫や鼻ぺちゃの短頭種、
また子猫は体温調節が難しく、
リスクが格段に高まります。
「うちの子は室内飼いだから安心」
そう考える飼い主さんも多いですが、
閉め切った部屋やキャリーケースの中でも
熱中症は起こるのです。
この記事では、猫が見せる熱中症のサインを
わかりやすく紹介し、
飼い主さんがすぐに気づけるための
ポイントを解説していきます。
大切な命を守るために、
ぜひ最後まで読んでチェックしてください。

サイン① 舌を出して「ハァハァ」
猫は基本的に口呼吸をしません。
もし、舌を出して「ハァハァ」と
呼吸をしていたら、それは危険信号です。
体温が急激に上昇し、
体が熱を逃がそうと必死に働いている状態。
人間でいえば息苦しく、
立っているのもしんどいほどの状況です。
このサインを見たらすぐに
エアコンをつけて室温を下げ、
新鮮な空気が通る環境にしてください。
ただし氷水をかけるなどの急激な冷却はNG。
体調をさらに悪化させる可能性があります。
まずは穏やかに体を冷やし、
すぐに動物病院へ相談してください。

サイン② よだれが出ている
猫のよだれは普段あまり目にしません。
そのため、口元に異変を感じたら要注意です。
・サラサラしたよだれ → 初期の脱水
・ネバネバして糸を引く → 脱水が進行中
こうしたサインは熱中症による体液バランスの
乱れが原因のことが多いです。
放置すると血液がドロドロになり、
臓器に大きな負担をかけてしまいます。
普段から「口元のチェック」を
習慣にしておくと、
小さな変化にも早く気づけます。

サイン③ 背中の皮膚チェック
猫の脱水を知る簡単な方法が
「皮膚テントチェック」です。
背中の皮膚をそっとつまみ、
離したときにすぐ戻れば正常。
戻りが遅い、あるいは形が残るようなら、
すでに脱水が進行しています。
特に暑い季節は、
水分不足から脱水に陥りやすい時期です。
皮膚チェックは毎日の健康管理に
簡単に取り入れられる方法なので、
習慣化しておくと安心です。

室内でも熱中症になる!?
熱中症は屋外だけの問題ではありません。
むしろ完全室内飼いの猫こそ危険なのです。
・締め切った部屋
・風の通らないキャリーケース
・日当たりの強い窓辺
これらの環境は猫にとって危険地帯です。
真夏の閉め切った部屋は
短時間で40℃近くに達することも。
たとえ「涼しい場所に移動できるだろう」と
思っても、猫は思うように移動せず、
同じ場所で耐えてしまうことがあります。
「室内だから安心」という油断は禁物です。

鼻ぺちゃ猫や高齢猫は要注意
ペルシャなどの短頭種は
もともと鼻が短いため、
空気をうまく取り込めません。
体温調整が苦手で、
特に熱中症リスクが高い子です。
また、高齢猫は体の機能が低下しており、
暑さや脱水に対する耐性が弱くなります。
子猫も同様に体力が少なく、
すぐに体調を崩してしまいます。
「うちの子はもう年だから」
「子猫だからまだ平気だろう」
そんな思い込みが危険を招きます。
ライフステージに合わせた配慮が必要です。

目安は室温28℃以下
猫の熱中症を防ぐには、
室温管理が欠かせません。
エアコンはためらわずにON。
28℃以下を目安にしましょう。
ただし、風が苦手な子もいます。
猫自身が心地よい場所に移動できるように
部屋の中に涼しいスペースを
複数つくってあげるのがおすすめです。
また、冷却マットや凍らせたペットボトルを
タオルで包んで置くのも有効です。
獣医師として伝えたいこと
熱中症は、とても恐ろしい病気です。
単なる「暑さでしんどい」というレベルではなく、
体の仕組みそのものを壊してしまう危険があるのです。
私たちの体も猫の体も、
その大部分はタンパク質でできています。
このタンパク質は、高温になると変性し、
元の形には戻れなくなってしまいます。
たとえば卵を加熱すると白身が固まるように、
一度変性してしまったタンパク質は
元の状態に戻ることはありません。
体の中で同じことが起これば、
内臓や脳に深刻なダメージが残り、
最悪の場合、命を落とすことにつながります。
もちろん、異変に気づいたら
すぐに動物病院に受診することが大切です。
しかし、本当に重要なのは
「熱中症にならない環境」をつくること。
室温管理、水分補給、風通しの工夫。
その一つひとつが愛猫の命を守ります。
「猫は暑さに強いから大丈夫」ではなく、
「熱中症にさせないための工夫を必ずする」
この意識を持つことが、
飼い主さんにできる最も大切な予防策です。
環境づくりこそ最大の予防策
猫の熱中症を防ぐうえで一番大切なのは、
「そもそも熱中症にならない環境」を
用意してあげることです。
そのためには、飼い主さんのちょっとした
工夫や意識が大きな差を生みます。
まず、室内の空調は単純に温度だけでなく、
風通しや空気の流れにも注意しましょう。
同じ部屋でもエアコンの風が当たる場所と
そうでない場所では、温度差が
5℃以上あることも珍しくありません。
猫は快適な場所を選んで過ごす習性があるので、
複数の涼しいスポットをつくってあげることが
大切です。
また、ケージでお留守番させる場合には
特に注意が必要です。
ケージの中が暑くなってしまったとき、
そこから逃げられないため、
あっという間に体温が上がってしまいます。
どうしてもケージで過ごさせるときは、
直射日光を避け、必ず風が通るように配置し、
温度計を置いて確認する習慣をつけましょう。
一方で、にゃんガードのようなゲートを
活用すれば、危険な場所を区切りながら
室内の広い範囲を安全エリアにできます。
猫が自分の意思で涼しいところ、
風通しの良いところに移動できるようにすることは、
熱中症予防に直結します。
さらに、高齢猫は人間の高齢者と同じく
暑さに気づきにくい特徴があります。
日の当たる窓辺で眠ってしまい、
そのまま体が熱にさらされて危険な状態になる
ケースも実際にあります。
高齢猫や体力の落ちた猫ちゃんは特に、
日当たりや空調の当たり方を
飼い主さんが意識して調整してあげる必要があります。
猫自身が「快適だ」と思える環境は、
人が思う以上に繊細です。
だからこそ、日々の小さな工夫が
大切な命を守る第一歩になるのです。
まとめ
猫の熱中症は「暑いだけ」ではなく、
命に直結するとても危険な病気です。
体をつくるタンパク質は熱によって変性し、
一度壊れると元に戻ることはありません。
だからこそ「気づいた時には手遅れ」
という事態が起こるのです。
猫は暑さに強いと誤解されがちですが、
実際にはとても弱く、
しかも不調を隠す習性があります。
元気そうに見えても安心せず、
口呼吸やよだれ、皮膚の戻りなど
小さなサインを見逃さないことが大切です。
また、予防は環境づくりから始まります。
エアコンで室温を28℃以下に保ち、
風通しの良い場所や涼めるスペースを
いくつか用意してあげましょう。
にゃんガードなどで安全な範囲を広げれば、
猫自身が快適な場所を選んで移動できます。
特に高齢猫や鼻ぺちゃの短頭種、
子猫はリスクが高いため、
飼い主さんがこまめに観察し、
日差しや空調の当たり方にも
注意を払ってあげてください。
熱中症は「ならない工夫」が一番の治療です。
小さな意識と日々の配慮が、
大切な命を守る大きな力となります。
今日からできることを少しずつ取り入れて、
安心して暮らせる環境を整えてあげましょう。




